音楽MUSIC
長谷川和芳 | 転がる石のように名盤100枚斬り 第92回 #9 Blonde on Blonde (1966) - BOB DYLAN 『ブロンド・オン・ブロンド』- ボブ・ディラン
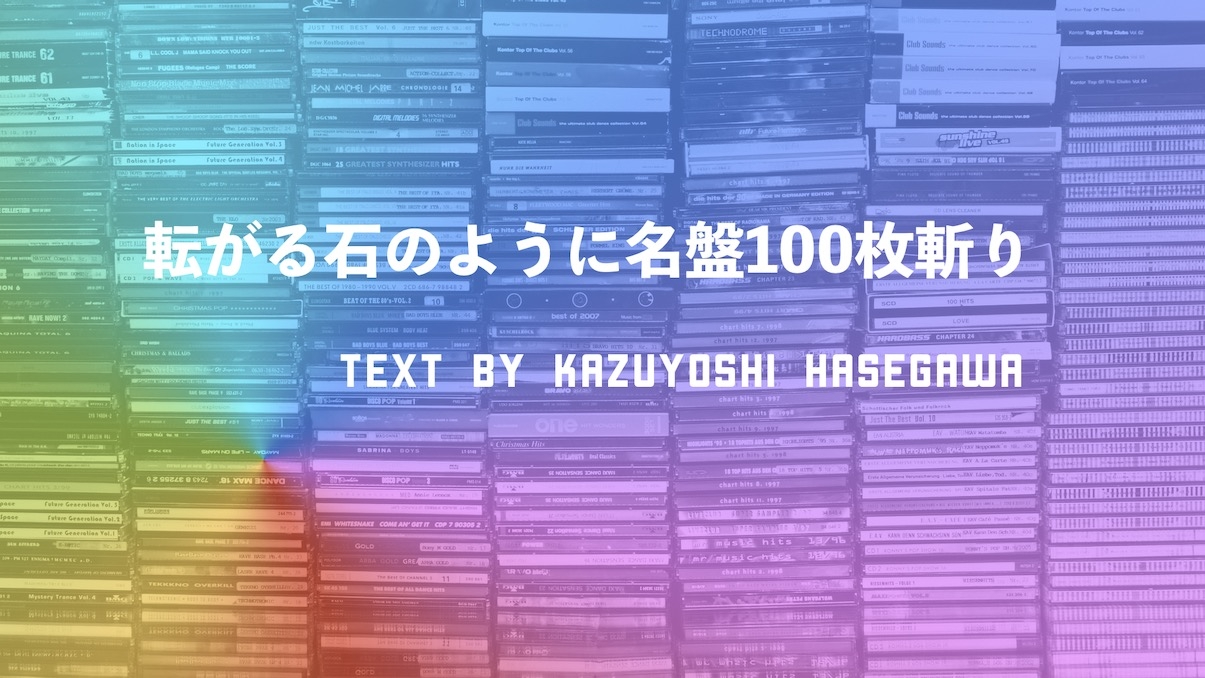
ボブ・ディランがデビュー・アルバムをリリースしたのは1962年なので、2022年はデビュー60周年ということになる。この間に制作されたスタジオ・アルバムは39枚。ほかにライヴ盤やコンピ盤、さらには公式海賊版であるブートレッグ・シリーズもリリースされており、そのカタログ数は全部合わせると3桁に迫っているんじゃないだろうか。
そのなかで、ディランの最高傑作はどれなのかというと、意見が分かれるものの、一般的には60~70年代の作品の評価が高い。個人的には、ダニエル・ラノワのプロデュースが光る『タイム・アウト・オブ・マインド Time Out of Mind』(1997年)以降のアルバムの方が、リアルタイムで聴いてきた分、思い入れも深いのだけど、世間様の評価では、『血の轍 Blood on the Tracks』(1975年・)、『追憶のハイウェイ61 Highway 61 Revisited』(1965年)、そして『ブロンド・オン・ブロンド』(1966年)がディラン・クラシックとして定着している。
ローリング・ストーン誌が選ぶ『史上最も偉大なアルバム』(2003年発表・2012年改訂版)を見てみると、今回のお題である『ブロンド・オン・ブロンド』が9位なのに対し、『血の轍』は16位でこの連載でも紹介済み。『追憶のハイウェイ61』はディランのアルバム中最高位の4位にランクインしている。
一方、2020年発表の『史上最も偉大なアルバム』最新版では、『ブロンド・オン・ブロンド』は29ランクダウンの38位、『血の轍』は7ランクアップの9位、『追憶のハイウェイ61』は14ランクダウンの18位。『追憶のハイウェイ61』>『ブロンド・オン・ブロンド』>『血の轍』だったのが、『血の轍』>『追憶のハイウェイ61』>『ブロンド・オン・ブロンド』になってしまった。
ランキング好きのローリング・ストーン誌は、読者が選んだディランのベスト・アルバムなんて企画も2012年に行っていて、いつもの3枚がトップ3を占めているのだけど、ここでの順番は、『血の轍』>『ブロンド・オン・ブロンド』>『追憶のハイウェイ61』。いずれにせよ、この3枚がディランの最高傑作群とみなされていることは疑いがない。
『血の轍』と『追憶のハイウェイ61』は、それぞれ「ブルーにこんがらがって Tangled Up in Blue」「ライク・ア・ローリング・ストーン Like a Rolling Stone」というロック史上でも屈指の名曲がアルバムのオープナーだってのがでかい。先頭打者ホームランて感じ。
加えて、ディランが大きく変わろうとしている姿を活写していることも2枚のアルバムをスリリングなものにしている。『血の轍』はアーティストとしてのアイデンティティ・クライシスを抜け出そうとしていた時期の作品だし、『追憶のハイウェイ61』はフォークからロックに完全に舵を切ろうと試みた作品だ。そのためか、両アルバムとも演奏がタイトで緊張感があるし、ディランのヴォーカルもピリピリとした切迫感を放っている。この2枚を聴くと、その名盤っぷりに、僕は思わず居住まいを正してしまうのだった。
さて、『ブロンド・オン・ブロンド』はどうか。アルバム1曲目の「雨の日の女 Rainy Day Women #12 & 35」が象徴的だ。マーチのリズムにのってけたたましくホーンが鳴り、そこに珍しく陽気なディランのヴォーカルがかぶさる。この曲を聴くと、楽隊が気ままに演奏しながらパレードしている風景が浮かぶ。楽隊のメンバーのおそらく半数以上は酔っ払っているんじゃないか。まさに”お祭り騒ぎ”。この祝祭感は『血の轍』と『追憶のハイウェイ61』にはない。
この曲に限らず、アルバム全体を通して、ディランはオープンでリラックスしているように思える。なんかゆるい。その声には温かみがあり、聴いていて心地よささえ感じる。
収録曲で唯一違和感を覚えるのは、このアルバムからのファースト・シングル「スーナー・オア・レイター One of Us Must Know (Sooner or Later)」で、ディランの声がハツラツとしているうえにアレンジが大袈裟で、アルバムの並びで聴くと明らかに浮いている。ほかはナッシュビル録音だけど、この曲だけニューヨークでのレコーディングらしい。環境の違いが如実に表れている。
ナッシュビルはアメリカ南部の街でカントリー・ミュージックのメッカだ。『ブロンド・オン・ブロンド』では、そこで活動するセッション・ミュージシャンをバックに起用しているんだけど、それがオーガニックな演奏として実を結んでいる。「スーナー・オア・レイター」を除けば、どの曲も味わい深いし、風通しがいい。
加えて言うと、フォークの中心地であるニューヨークから離れたことが大きかったのかもしれない。フォークとかロックとかカントリーとかブルースとか、そういうジャンルにとらわれず、より自由に純粋に音楽を楽しめる環境が、ナッシュビルにはあったのだ。だから、『ブロンド・オン・ブロンド』の収録曲はバラエティに富んでいて、2枚組14曲という大作だけど、飽きさせない。
バックを務めたのはナッシュビルのミュージシャンだけではなく、ニューヨークからもアル・クーパーが参加している。アル・クーパーとディランの関係は「ライク・ア・ローリング・ストーン」から始まる。曲のトーンを決めたオルガンは彼によるもので、実は飛び入り参加だったらしい。『ブロンド・オン・ブロンド』でも、随所で鮮やかな鍵盤さばきを披露している。
特に、6曲目に入っている「メンフィス・ブルース・アゲイン Stuck Inside of Mobile With Memphis Blues Again」での、オルガン・プレイはさりげないけど実におしゃれ。曲自体にソウルぽい雰囲気もあって、アル・クーパーのソロにも通じる。聴いているうちになんだか楽しくなってくるんだよなぁ。ディランの曲でこんな感想を抱くことも珍しい。
ただし、曲が楽しいからと言って、リリックも楽しいとは限らないのがディラン。「メンフィス・ブルース・アゲイン」も他者とコミュニケーションが取れず人生に行き詰まってしまった男のつぶきだったりする。
“あぁ、ママ、本当にここで行き止まりなのかい?/クルマの中に閉じこもって/メンフィス・ブルースをまた聴いている”
・・・・・・楽しくはない。
収録曲のなかでも人気の高い「アイ・ウォント・ユー I Want You」はカントリーロック調の軽快なナンバーで、思わず口ずさんでしまうけど、リリックは、誰にも愛されず嫉妬に駆られた男が、自らの欲望を吐露しているという内容。
ブルージーな「ヒョウ皮のふちなし帽 Leopard-Skin Pill-Box Hat 」は、帽子に固執するちょっとサイコな男が主人公だし、いかにも60年代中期のロックン・ロール「アブソリュート・スイート・マリー Absolutely Sweet Marie」は、刑務所から贈るマリーへのラヴレター。ディランのバラードのなかでも屈指の名曲「女の如く Just Like a Woman」の主人公は実はゲイの男性だという解釈もある。
“僕の倉庫のようにのなにもかもをしまい込む目、僕のアラビアのドラム/そんなものはあなたの門のそばに残して行くべきなのか/それとも、悲しい目をした貴婦人よ、僕はあなたを待つべきなのか”
こう歌う「ローランドの悲しい目の乙女 Sad Eyed Lady of the Lowlands」は、レコーディングの直前に結婚した愛妻・サラに捧げた曲らしい。
は?
テーマとリリック、曲調が乖離しているのは『血の轍』も同じだし、まぁ、要するにボブ・ディランというのは、こういう芸風の人で、「ブルーにこんがらがって」いるのは、まさにディラン本人だったりするんだろう。『ブロンド・オン・ブロンド』のジャケットのディランも「こんがらがって」いる。ブレた写真の中のディランは眉間にシワを寄せて遠くを見やっていて、いかにも哲学者然としているけど、1曲目から愉快な「雨の日の女」だもの。その眉間のシワはなんだったんだ?
だから、リリックは、脇に置いておこう。ディラン信者じゃなければ、よほどヒマなときに目を通せばいい。結局のところ、そこでどんなに悲しい情景が歌われていたって、『ブロンド・オン・ブロンド』というアルバムが「めでたい」フィーリングに満ちていることは間違いないし。そのポジティヴなヴァイブレーションは、きっとディランのヴォーカルとバンドの演奏によるいわゆる”化学反応”が生んだものだろう。ディランは『ブロンド・オン・ブロンド』を評して、「ずっと頭の中で鳴っていたサウンドをようやく再現できた」と1978年に語ったそうな。理想の音楽を鳴らすことができたディランの喜びが、「めでたい」感じの源泉なのかもしれないね。
『ブロンド・オン・ブロンド』には、「ブルーにこんがらがって」「ライク・ア・ローリング・ストーン」なんていう超名曲は入ってない。でも、『血の轍』『追憶のハイウェイ61』よりも親しみやすいし、この3枚のなかでは一番好き。加えて、ジャンルには収まらない「ディランのロック」が確立されたという意味でも重要だと思う。
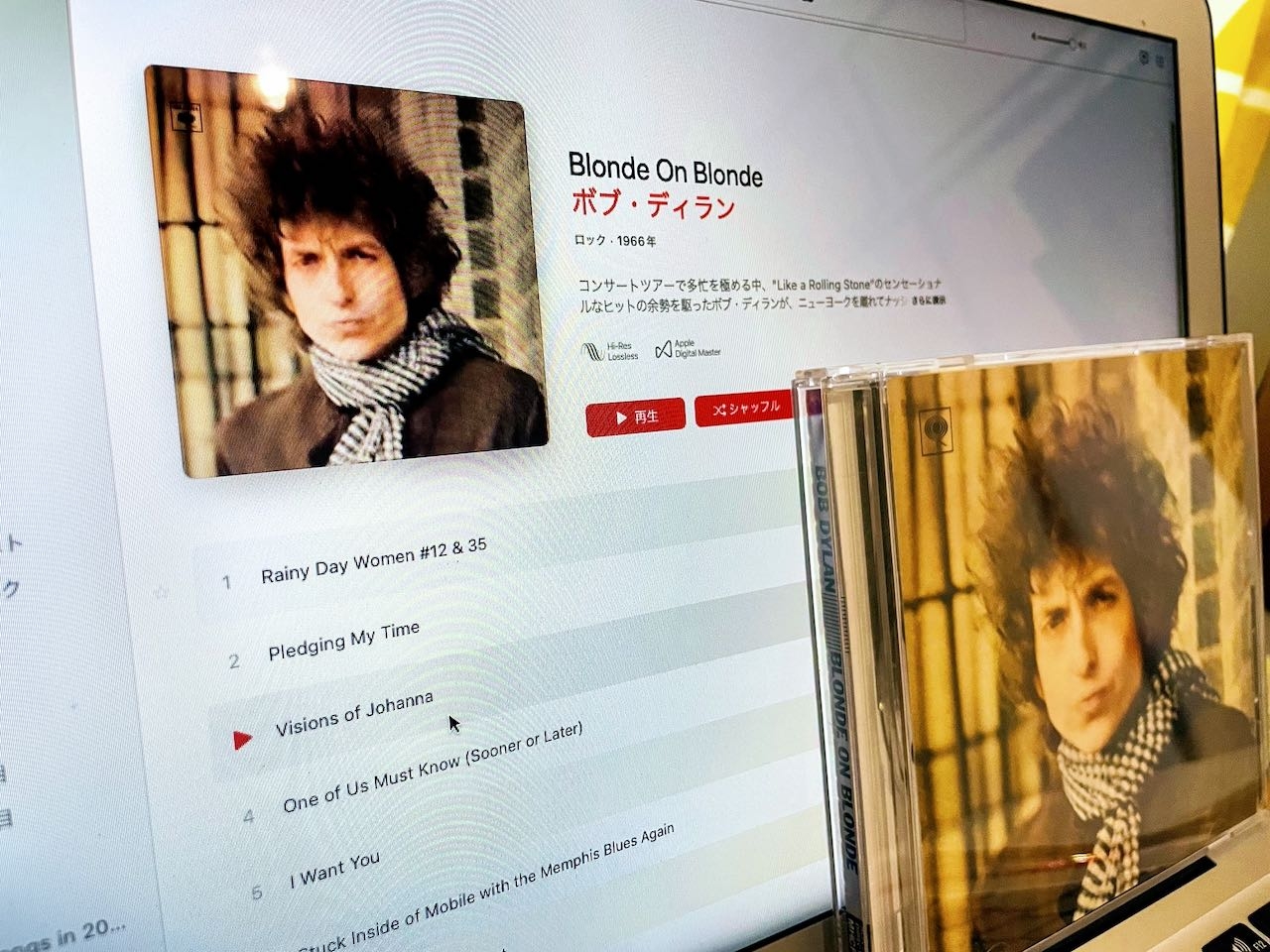
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★★


