音楽MUSIC
長谷川和芳 | 転がる石のように名盤100枚斬り 第94回 #7 Exile on Main St. (1972) - THE ROLLING STONES 『メイン・ストリートのならず者』- ザ・ローリング・ストーンズ

ローリング・ストーン誌が選ぶ『史上最も偉大なアルバム』(2003年発表・2012年改訂版)、10位『ザ・ビートルズ』、9位『ブロンド・オン・ブロンド』、8位『ロンドン・コーリング』に続いて、なんと7位も2枚組。ストーンズのキャリアにおける唯一の2枚組アルバムがランクインした。
なんで2枚組になってしまったのか、WEBを掘ってみてもその答えは見つからなかったけど、2枚組の方が値段上げられるし、利益率も高いとかいう理由なんじゃなかろうか。この人たち、税金対策でフランスに移住するくらいだし。
この『メイン・ストリートのならず者』が、ストーンズの最高傑作の一つに数えられているのは知っていたけど、いままで聴いたことはなかった。理由は簡単で、「サティスファクション」とか「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」とか「ブラウン・シュガー」みたいな、ストーンズ・ファン以外にも浸透しているド名曲が入っていないから。なんとなくスルーしていた。
聴く前にストーンズ好きの人のレヴューに目を通すと、「傑作だけど初心者向けではない」という評価が多い。なんだこのスノッブな感じは。ストーンズ・マニア向けということ? 僕みたいな通りすがりのおっちゃんには理解できない深遠な世界が広がっているってこと? でも、言うてもストーンズですよ。プロデューサーも前作『ステッキー・フィンガーズ Sticky Fingers』に続きジミー・ミラーだし、音もその延長線上でしょ。そんなに身構えることもないだろうってなもんで、例のごとくAppleMusicで実際に聴いてみましたよ。
いやいや、『ステッキー・フィンガーズ』とは、まったく空気感が違う。
リリース当時、「ユルすぎて散漫な印象」などという評価もあったそうな。確かに『ステッキー・フィンガーズ』が違って、カチッとプロデュースされている感は薄い。セッションをそのままレコードに落とした印象。加えて、ロカビリーからスワンプ・ロック、フォーク、カントリー、ブルース、ゴスペルまで、楽曲のテイストは多岐にわたる(ミック・ジャガー曰く「ポップス以外の要素は全部入っている」)。まるで、アメリカの大衆音楽を全網羅しようとしたかのようだ。
だからと言って、決して「散漫な印象」を受けたかというとそんなことはなかった。それは、どうもミックのプロデュース能力に負うところが大きいような気がする。
レコーディングが行われたのは、ストーンズの面々が移住したフランス。キース・リチャーズの住処にスタジオをつくって、そこに昼となく夜となくミュージシャンが集まってセッションを行った。ここでリーダーシップを取ったのはキースだ。でも、このころのキースはドラッグまみれで、レコーディング中にもたびたびキメていたっぽい。その影響もあって、セッションの雰囲気はあまりよろしいものではなかったようだ。その後、アメリカはロサンジェルスに場所を移し、今度はミック主導でオーヴァーダブを行うとともに追加の曲をレコーディングしている。
制作プロセスをたどると、『メイン・ストリートのならず者』がアルバムとしてトータル感を失わなかったカギは、ロサンジェルスでのスタジオ作業にあるように思える。前述したように並んでいるナンバーはバラエティ豊かなだけど、ミック、そしてプロデューサー、ジミー・ミラーは、それらを緻密な計算のうえで組み合わせることによって、大きな流れをつくることに成功している。
2枚組アルバムなので、レコードは全部で4面あるわけだけど、収録曲を面ごとに分けて聴くと、彼らの意図が見えてくる。
A面は軽快なロックン・ロールで幕を開け、ロカビリーを挟んでブルースをキメて、スワンプ・ロック「ダイスをころがせ Tumbling Dice 」へと続く。景気がいい。打って変わってB面はフォーキー&カントリーがキーワード。アメリカーナの牧歌的な世界(歌詞は不穏なものもあるけども)。
盤を変えてC面。トップにストーンズ原理主義者絶賛の「ハッピー Happy」を置くのもニクい。その後が圧巻。ファストでファンキーなカントリーから重めのブルースへつなぎ、コーラスとパーカッションが不穏な空気を醸し出すインタールード的な立ち位置の曲を経て、感動的なゴスペルでフィニッシュ。
D面はアタマはストーンズらしいロックン・ロール。そして、ファンキーなブルース(ロバート・ジョンソンの曲のカヴァー)で徐々にテンションを高め、ビリー・プレストンのオルガンが崇高な空気を醸し出す正真正銘の名曲「ライトを照らせ Shine the Light」へなだれ込む。ここで大団円じゃないところがまたニクい。ラストは再びストーンズならではの肩から力が抜けたロック・チューン「ソウル・サヴァイヴァー Soul Survivor」。
アルバムとしてみごとにパッケージされている。すべて計算ずく。どこが散漫なのだ。
確かに、半分ラリったキースが主導した演奏は、全体的にルーズな雰囲気。でも、それがナマっぽくていい。ミックとジミー・ミラーは、うまくそのライヴな感じを生かしてアルバムをまとめている。ミックのそんなやり手なとこがちょっとイヤミではあるけども。
じゃあ、『メイン・ストリートのならず者』がミックのアルバムなのかと問われたら、「そりゃ違う、あくまでもキースのアルバムだ」と僕は答えたい。ミックは、キースのアタマの中から溢れ出してきた音楽を商品棚にきれいに並べたに過ぎない。
オースティン・バトラーがエルヴィス・プレスリーをみごとに演じ切った、バズ・ラーマン監督の映画『エルヴィス』の前半部では、ロックン・ロールがアメリカ大衆音楽のハイブリッドであることをうまく観せていた。鍋の中にブルースとゴスペルをぶっ込んで、そこにカントリーを加えて混ぜ合わせればできあがり。
『メイン・ストリートのならず者』レコーディング時、キースのアタマの中でも、エルヴィスに降りてきたものと同じレシピの「ロックン・ロール」がぐつぐつと煮立っていた。それをロカビリーにブルース、カントリー、ゴスペルとさまざまなスタイルでアウトプットする。それらはロックン・ロールを構成する元素みたいなものだから、アルバム一枚を通して聴くと、立ち上ってくるのは「ロックン・ロール」としか言えない音楽なのだな。
さらに言うと、フランスで録音されたことも、このアルバムを名盤たらしめていると思う。しかも、キースはクスリでヘロヘロである。アメリカから遠く離れているからこそ、キースの中で煮えたぎるロックン・ロールの純度は高くなる。現実に左右されない「理想のロックン・ロール」がアタマの中で渦巻く。ラリっていることがそれに拍車をかける。
「俺自身がアメリカだ。俺が再びロックン・ロールを産み出すのだ」・・・・・・とキースが意気込んでいたとは思えないけど、結果的に後にも先にもない高純度のロックン・ロール・アルバムが産まれることとなった。奇跡的な一枚と言ってもいいんじゃないかな。
ストーンズ・メンバーに加え、ニッキー・ホプキンス(キーボード)やボビー・キーズ(サックス)など、キースのロックン・ロール魂を具現化できる実力派のミュージシャンたちが参加していたことも大きい。特に、このころのストーンズの準レギュラーとも言えるニッキー・ホプキンスの鍵盤は、サウンドに奥行きを与え、このアルバムにエモーショナルな色彩を添えている。
聴く前はストーンズの最高傑作は『ステッキー・フィンガーズ』でいいんじゃない?なんて思っていたんだけど、『メイン・ストリートのならず者』でキマり。大傑作じゃないですか。
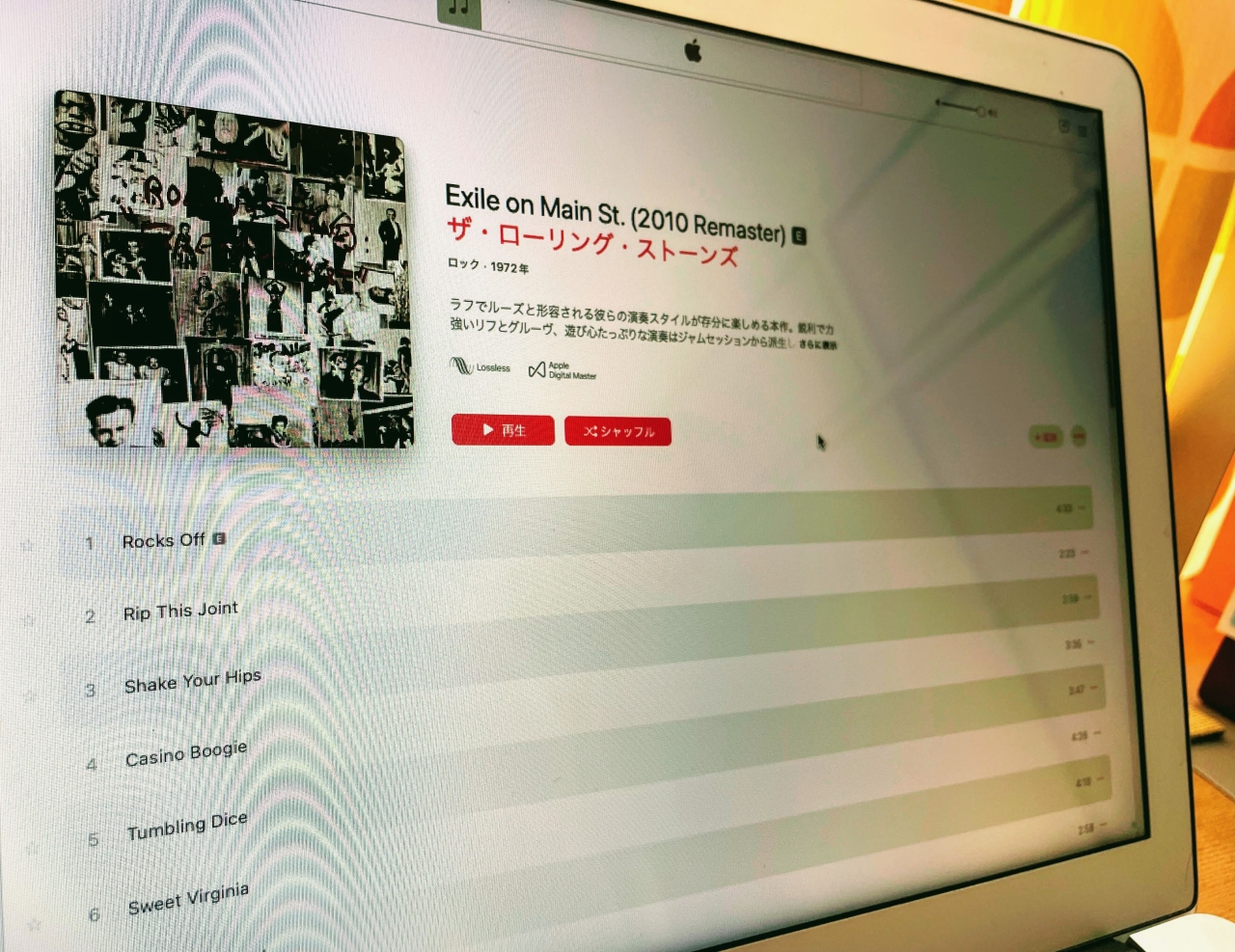
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★★


