音楽MUSIC
長谷川和芳 | 転がる石のように名盤100枚斬り 第100回 #1 Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) - THE BEATLES 『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』- ザ・ビートルズ
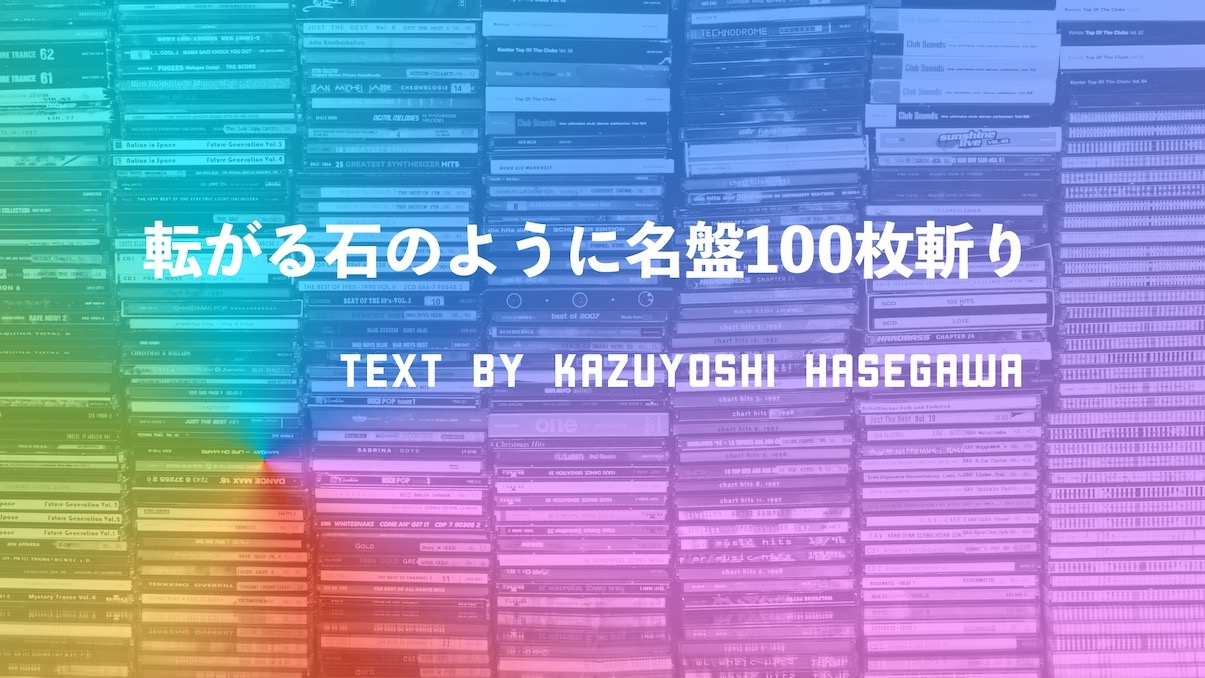
2019年4月より、ローリング・ストーン誌が選ぶ『史上最も偉大なアルバム』(2003年発表・2012年改訂版)の上位100枚をカウントダウンしてまいりましたが、ついに100枚目。今回のお題はザ・ビートルズ『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハート・クラブ・バンド』である。
1967年にリリースして以来、”ロックの金字塔”という評価を不動のものとし、ローリング・ストーン誌のレヴューでも「もっとも重要なロックン・ロール・アルバム」と絶賛されていた・・・・・・のだけども、2020年発表の『史上最も偉大なアルバム』最新版では王位剥奪。なんと24位まで評価を落としてしまった。
斬新な音楽的なヴィジョンに導かれスタジオで実験を繰り返した結果、当時の録音技術の限界を突破し、ロックをアートの領域まで高めた —— 従来の『サージェント・ペパーズ~』の評価はこんなところだろう。しかし、こんな評価を耳にしたところで、2020年代のリスナーからすれば、「で?」という反応しか返せないんじゃないだろうか。
ビートルズが刷新したのはあくまでも「60年代当時」の録音技術だし、いまやアートとポップ・カルチャーの垣根はないも同然で、「アートとして認められた! すごい!!」と言われても困惑するばかり。
「サマー・オヴ・ラヴ *」のサウンドトラックと評されただけあって、アルバム自体が1967年という時代の空気感に侵されており、そりゃ、古ぼけて聴こえたとしても不思議はないよなぁ。
* アメリカ・サンフランシスコのヒッピーが中心となって、ドラッグをキメ、脳天気に「ラヴ&ピース」と繰り返したムーヴメント
なによりも、「架空のバンドによる一夜のショウというコンセプトのトータル・アルバム」と喧伝されていたのに、実際はそのコンセプトが、明らかに破綻しているのが痛い。
レコードの時代であれば、ジャケットの凝った仕様と付録でごまかせたかもしれない。しかし、現代はサブスクが主流。パッケージは意味なし。「俺が書いた曲はそんなコンセプトとはいっさい関係ないよん」というジョン・レノンの発言を聞くまでもなく、音源を一聴すれば「架空のバンド」という設定が、なし崩しになっているのがわかる。
タイトル・トラックから、リンゴの代名詞的なナンバー「ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンド With a Littele Help from My Friend」に続くあたりは「それ」っぽい。それ以降は、12曲目でタイトル・ナンバーが再度登場するまで、聴く人のアタマから「架空のバンド」なんてのは消え去っている。「なんだ、ビートルズじゃん」
例外は、8曲目(レコードのB面1曲目のジョージ・ハリソンのラーガ・チューン「ウィズイン・ユー・ウィズアウト・ユー Within You Without You」。SEの効果もあり、インドから招聘した楽団がゲスト出演しているふう。しかし、このSEも、「哲学的なリリックをマジに受け止められるとイヤなので、観客の笑い声でごまかそうとした」というのが真相みたい。
ラストの「ア・デイ・イン・ザ・ライフ A Day in the Life」は「アンコール」という設定だって。いやぁ、無理ありすぎでしょう、こんな大作をアンコールにもってくるなんて。
「ペパー軍曹のロンリー・ハーツ・クラブ・バンドという架空のバンドになりきっちゃおう!」というアルバム・コンセプトは、以前も触れた通り、ポール・マッカートニーによる思いつきだ。個人的にはなにがおもしろいのかよくわからないんだけど、なぜ、ポールはこんなアイディアに思い至ったんだろう。
「架空のバンド」が何者なのかという問いに対する答えは明白で、当時の最先端のドラッグであるLSDを使って意識を拡張したビートルズ自身のことだろう。前作『リボルバー』に続いて、『サージェント・ペパー~』がLSDの影響下にあることは、「メンバーはわたしに隠れてLSDやってたよ」という、プロデューサー、ジョージ・マーティンの証言からも明らかである。
「LSDのおかげでかつてない斬新なヴィジョンが浮かんできた。もう俺たちはビートルズじゃない、ペパー軍曹のバンドだ!」
そういうことなんだな。
薬物はやったことがないので、僕にはそのへんの機微はわからない。しかし、なぜか我が家には『チョコレートからヘロインまで——ドラッグカルチャーのすべて』(A・ワイル、W・ローセン著・第三書館)なる書物があったので、「LSD」の項目に目を通してみた。
曰くLSDは「現存するドラッグの中でも、最も効力の強いもののひとつ」だそうな。 不純物が少ないものを使用し適正な量を守れば、ほとんどの場合、ポジティヴな体験につながるらしい。この本で報告されているLSDによるトリップの内容は以下の通り。
「愛への強烈な情熱」「すべてのものとの神秘的調和」「神との一体感」「己自身への深い理解」「鮮明な知覚の変化」
『サージェント・ペパー~』に話を戻すと、ジョンが書いたナンバーからは、確かに上記のようなLSDの影響が感じ取れる。
頭文字がモロLSDという(ジョンは否定しているけど)、サイケデリックな「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンド Lucy in the Sky with Diamonds」を筆頭に、カーニバルの喧騒と狂気を連想させる「ビーイング・フォー・ザ・ベネフィット・オヴ・ミスター・カイト Being for the Benefit of Mr. Kite」、現代社会を覆う虚無感を皮肉った「グッド・モーニング・グッド・モーニング Good Morning Good Morning」まで、明らかに『リボルバー』とは異なったサウンド・スケープを描き出している。
一方、「架空のバンド」の言い出しっぺ、ポールのナンバーはどうか。これがまた「普通」なのだ。一部、サイケな味付けもしてるけど、基本的にはオーセンティック。ジョンほどぶっ飛んではいない。
結局のところ、ポールのLSDとの付き合い方は、『リボルバー』のときと変わっていないんじゃないか。ポールがLSDの使用を拒否する一方で、ほかの3人は仲良くトリップ。このポールと3人のテンションのギャップが、『リボルバー』がおもろカッコいい傑作となった要因だと、この連載の前々回で述べた。
ジョージ・マーティンの証言通り、『サージェント・ペパー~』のレコーディング時にポール以外の3人はLSDをキメていたかもしれないけど、ポールはどうだったんだろう? 相変わらずLSDと距離をとっていたとしてもおかしくはない。
LSDには根強い抵抗感をもっていたにもかかわらず、3人との溝を埋めるために「架空のバンド=LSDキメた俺たち」というコンセプトを、ポールは思いつく。もちろん、当時のユース・カルチャーを取り入れるというマーケティング戦略的な側面はあるだろうけど、それ以上にポールがほかの3人のメンバーの嗜好に「寄せた」ということではないだろうか。
ビートルズというバンドを前に進めるためには、このコンセプトが必要だったんだろう。でも、それは「3人のモチベーションに火をつけるきっかけとしてLSDを利用する」くらいの重みしかなかった。
だから、「架空のバンド」なんて、ポール自身、真剣には考えてなかったんだろう。実際のところ、このコンセプトをぶち壊しにしているのは、ポールのナンバーだし。ポールのクラシック音楽に対するコンプレクスが爆発した「シーズ・リーヴィング・ホーム She’s Leaving Home」なんかを聴くと、ペパー軍曹のバンドはどこに行った?とキョロキョロしてしまう。
あまりに有名なジャケット・デザインや、凝ったアルバム・パッケージのおかげで、「コンセプト・アルバム」ぽい体裁を保ってはいるけど、結局は1967年の躁状態を、LSDと最新のレコーディング技術の力を借りて写し取ったというのが、このアルバムの本質かもしれない。
かと言って、このアルバムが「トータル・アルバム」として失敗作だとも決めつけられないのが、おもしろいところ。実際に、これまで僕は繰り返しこのアルバムを別の意味での「トータル・アルバム」として聴いてきた。
明らかに邪道な聴き方ではある。しかも、その解釈が僕のオリジナルなのか、誰かが書いた記事によって吹き込まれたのかも、ようわからん。でもせっかくの機会なので、『サージェント・ペパー~』の楽しみ方の一例として一説ぶってみる(あぁ、ビートルズおじさん)。
すべての鍵は、ラストに収録された「ア・デイ・イン・ザ・ライフ 」にある。繊細でカオティックな構成をもつこの曲は、エンディングに収められた40秒に及ぶオーケストラの残響音によって伝説となる。
詰まるところ、僕にとっての『サージェント・ペパー~』は、「ア・デイ・イン・ザ・ライフ 」に尽きる。「架空のバンド=LSDキメた俺たちビートルズ」というコンセプトは破綻しているけど、「ア・デイ・イン・ザ・ライフ 」にフォーカスすると、このアルバムから新しい物語を紡ぐことも可能だ。
・・・・・・なんてカッコつけてるけど、要は「夢オチ」。
『サージェント・ペパー~』の楽曲はすべて「ア・デイ・イン・ザ・ライフ 」に収斂していく。『サージェント・ペパー~』=「ア・デイ・イン・ザ・ライフ 」と言ってもいい。
“今日、新聞でこんな記事を見つけた”というフレーズから「ア・デイ・イン・ザ・ライフ 」は始まる。しかし、それが本当に新聞記事なのか、夢なのか判然としない。なぜなら、その後に出てくる、ポール担当の中間部分は目覚まし時計のベルの音で始まり、バスに飛び乗って仕事に向かう風景が描かれているからだ。そして、主人公はバスに揺られながら、またまどろんでしまう。
再び、ジョンのパート。新聞記事の話を続ける。そして、こうつぶやく。
“I’d love to turn you on. 君にも味合わせてあげたいな”
新聞記事では”turn on”できないし、このフレーズがLSDによるトリップを指していることは間違いないだろう。これで、それまでの新聞記事の話が、LSD影響下で見た夢=幻影だということがはっきりする。
そして、同じことは、「ア・デイ・イン・ザ・ライフ 」に至る『サージェント・ペパー~』のほかの収録曲にも言える。ペパー軍曹のバンドも、お空にいるルーシーも、家出しようとする少女も、どこかで見かけたサーカスのポスターも、インド風の楽団も、駐車場係のリタも、全部「ア・デイ・イン・ザ・ライフ 」の主人公が、LSDでトリップしたときに見た夢もしくは幻影なのだ。夢だから整合性はない。ペパー軍曹のバンドが途中で姿を消しても気にしてはいけない。急に「僕がジジイになっても仲良くしてくれる?」なんてボケたことを歌い出しても気にしてはいけない。
つまり、『サージェント・ペパー~』に収められた一連のナンバーを聴くことは、ビートルズが見た幻影を追体験することを意味する。僕ら自身が「ア・デイ・イン・ザ・ライフ (長い人生のうちのある一日)」の主人公になるということ。
そして、僕らの意識は”turn on”する。僕らのなかのなにかのスウィッチが入る。目に入る風景が、どこか以前と違って見える。世界の音がよりリアルに迫ってくる。
ここで述べたような「コンセプト」をビートルズが言語化していたわけはないと思うけど、彼らが音楽を通して聴く人を”turn on”したいと願っていたのは間違いない。『サージェント・ペパー~』のスゴさはここにある。ビートルズは、LSDが自分たちの感覚を拡張したように、音楽によって人々の意識を変革しようとしていたのだ。そんなことを企てたアーティストはあとにもさきにもいないだろう。その壮大な試みは音楽史に大きなインパクトを残し、リリース後50年余りにわたり「史上最高のアルバム」として讃えられた。しかし、この傑作も、LSD全盛の1967年でなければ生まれなかったはずだ。
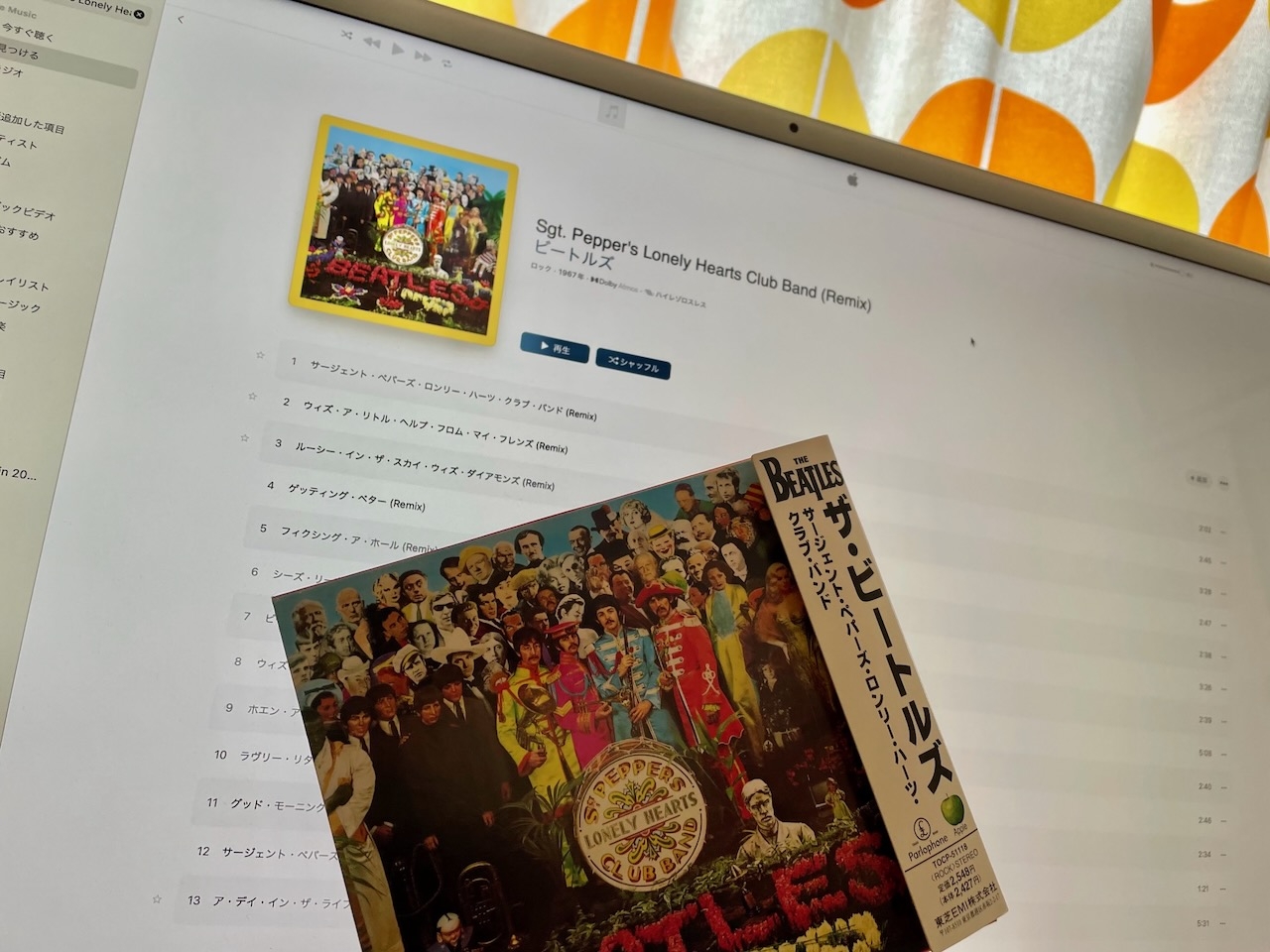
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★
――あとがき――
以上で100枚レヴューは終了。こんな機会でもなければ聴こうと思わなかった名盤に巡り会えて、とても有意義でした。以前はプログレが食わず嫌いだったんだけど、ピンク・フロイドのおかげで、聴けるように。
一方で、唯一、何度聴いても好きになれなかったアーティストがザ・フー。これは自分でも意外でした。もう少しじいさんになったら好きになるんだろうか?
まぁ「名盤」なんて人それぞれでで、音楽には「自分に合う/合わない」があるよね。一生聴ける音楽に出会えればそれでラッキーだし、こういう”ランキング”なんてのは、そのきっかけだと割り切って見るのがちょうどいいんじゃないでしょうか。
毎回、文章は短めにと思いながら書いていたんだけど、ついつい長くなってしまい(今回も)申し訳なく思っています。誤字脱字も数知れず。それにもかかわらず、BIGMOUTH WEBのスペースを提供してくれたクリゼンに心より感謝を。


