音楽MUSIC
転がる石のように名盤100枚斬り 第14回
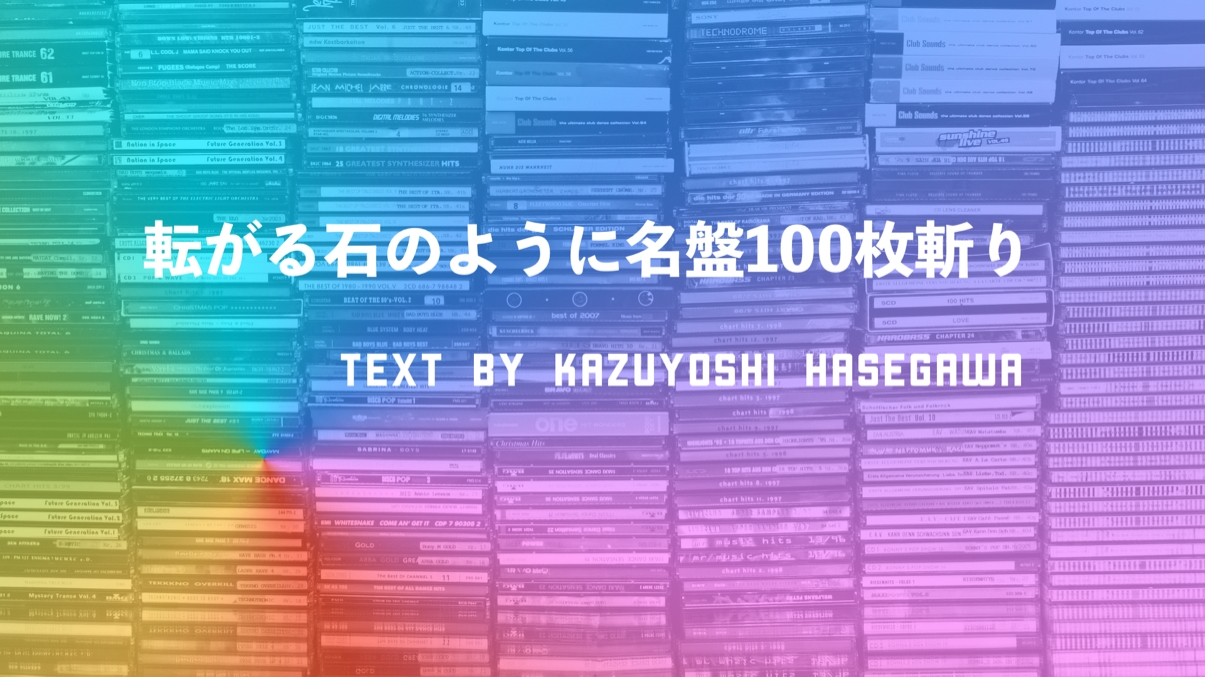
#87 The Wall (1979) - PINK FLOYD
『ザ・ウォール』 - ピンク・フロイド
高校2年生の時だったと思う。同じクラスの香月くんが、体育の授業中、グラウンドで話しかけてきた。
「長谷川くん、どんな音楽聴きよるん?」
答えに詰まった。そのころは、ザ・スミスばかり聴いていたんだけど、本当のことを言うのは、なんとなくはばかられた。
筑豊みたいな田舎で、「イギリスはマンチェスターのバンド、ザ・スミスが最近好きでねぇ」なんて言うと、気取ってるやつだと思われるんじゃないかと、心配になったのだ(実際は、ザ・スミスの音楽は決して「気取った」代物じゃなく、むしろ筑豊の片隅で聴くとグッサリと心に刺さるような音楽だったんだけど)。
そもそも、香月くんとは、そんなに仲良しってわけでもなかったし。
「イギリスのバンド・・・・・・とか」
と、お茶を濁す僕にたたみかける香月くん。
「ハードロック? ツェッペリンとか?」
「ツェッペリンはあまり聴かんねぇ」
「プログレは?」
「苦手」
「長谷川くん、ビートルズ好きなんやろ? なんでプログレ聴かんと?」
香月くんはプログレッシヴ・ロック、いわゆる「プログレ」が大好きだったんだけど、周りの連中は、プログレはおろか、洋楽さえ聴いていない(ラウドネスやアースシェイカーといった日本のハードロック・バンドの全盛期)。そんな時、長谷川がザ・ビートルズ好きだということを聞きつけ、同好の士ではないかと、話しかけたのだった(ザ・ビートルズ好き=プログレ好きというのは、よくわからんけど)。
ごめん、香月くん。未だにプログレは聴かんわぁ。
今の若い方々には、「プログレ」なんて、僕以上に「なにそれ?」って感じだろうか。クラシックや、ジャズ、現代音楽、民族音楽などの要素を組み入れた、感性よりもテクニック重視で、重厚長大なロックを指す・・・・・と、個人的には理解している。
なんで僕が、プログレを敬遠していたかというと、「重厚長大」な点が大きい。派手なシンセサイザーをフィーチャーしたり、オーケストラを使ったり、アレンジがえらく大仰な印象。一曲一曲の尺が長いイメージがあったのもよくない。若い時分は、パンクみたいに、短くてスカッと聴ける音楽の方がよかった。
一説によると、「プログレッシヴ・ロック」という用語は、日本のレコード会社のプロデューサーが、ピンク・フロイドの『原子母』というアルバムの煽り文句に使ったのが始まりだそうな。
今回のお題は、そのピンク・フロイドの『ザ・ウォール』。『ローリング・ストーンが選んだ史上最も偉大なアルバム』87位にランクインしている。
プログレなうえに「ロック・オペラ」だって。アルバム1枚でひとつの物語を展開するってやつ。プログレも、「ロック・オペラ」も苦手な僕は、もちろん、このアルバムを聴いたことは一度もない。
内容は、タイトル『ザ・ウォール』が象徴している。要は「壁」ですよ。分断の象徴ってやつですな、きっと(まだ聴いていない)。
現代人は常に「壁」に囲まれているかのような閉塞感に苛まれている。しかし、個人と個人の間にも「壁」があるために、助けを求めるすべすらない。そんな孤独な魂が、現代音楽の影響も受けた重厚なサウンドによって表現されているに違いない(まだ聴いていない)。
勝手に納得したところで、覚悟を決めて聴いてみた。あれ? 思ったよりも聴きやすい。メロディが立ったスタンダードな70年代ロック。デイヴィッド・ギルモアのギターがかっこいい。
コンセプト・アルバムだけあって、構成は緻密。ストーリーが進むにつれて、多彩な曲調が展開される。爆撃とか女性の声とか、小鳥の鳴き声とかSEが入ってくるのは、いかにも「ロック・オペラ」な感じ。
詞も読んだ(ウエブで検索すると全曲日本語訳がアップされています)。ヴォーカル&ベース担当のロジャー・ウォーターズが書いた自伝的なストーリーがベースになっているらしいけど、これがよくわからない。
主人公が学校で抑圧された生活を送ったことはわかった。
主人公の母親がモンスター・ペアレントなのもわかった。
戦争があったこともわかった。
見知らぬ街で見つけた恋人に逃げられたこともわかった。
主人公がロックミュージシャンらしいこともわかった。
主人公が精神に異常をきたし始めたことも。
なんども繰り返されるメッセージは「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール Another Brick in the Wall」、「みんな、結局は壁を形作る、ちっぽけなレンガに過ぎない」。ここから感じるのは「無力感」。
で、結末はどうかというと、禍々しく演劇的な躁状態が渦巻く曲「The Trial ザ・トライアル」のあとに収録されている、わずか1分44秒の最終曲「Outside The Wall アウトサイド・ザ・ウォール」で唄われるのは、「壁を越えるのは、マジ大変」という、やはり「無力感」「諦念」だったりする。出口なし。
「壁」が意味するものは、自分の心に巣食う「絶望」なのかもしれんね。それにしても、アルバムを聴き進めるにつれ、自分の気持ちが醒めていくように感じたのは、なぜなんだろう。
冒頭の「In the Flesh? イン・ザ・フレッシュ」から7曲目の「Goodbye Blue Sky グッバイ・ブルー・スカイ」あたりまで、要は、ロジャー・ウォーターズが、自らの出自と幼年期を描いたパートは、胸に迫るものがある。本人の人生が間違いなく反映されているからだろう。でも、そのあとは、聴きどころは多々あるにしても、所詮、主人公は架空のロックスターで、観念的な存在。血が通っているようには思えなかった。
ロジャー・ウォーターズ本人の実体験にもっとフォーカスして、曲数を半分にしたら、21世紀のリスナーにも届く傑作になったんではないか。それだと「ロック・オペラ」にはならなかったんだろうけど。
プレイリストで音楽を聴くことが当たり前になり、「アルバム」というフォーマットさえも存続が危ぶまれる昨今、「ロック・オペラ」というスタイルが現代のリスナーに支持されることは、おそらくない。アメリカのラッパーたちの自伝的な作品の方がリアルに響く。
ということで、香月くん、再び、ごめん・・・・・・
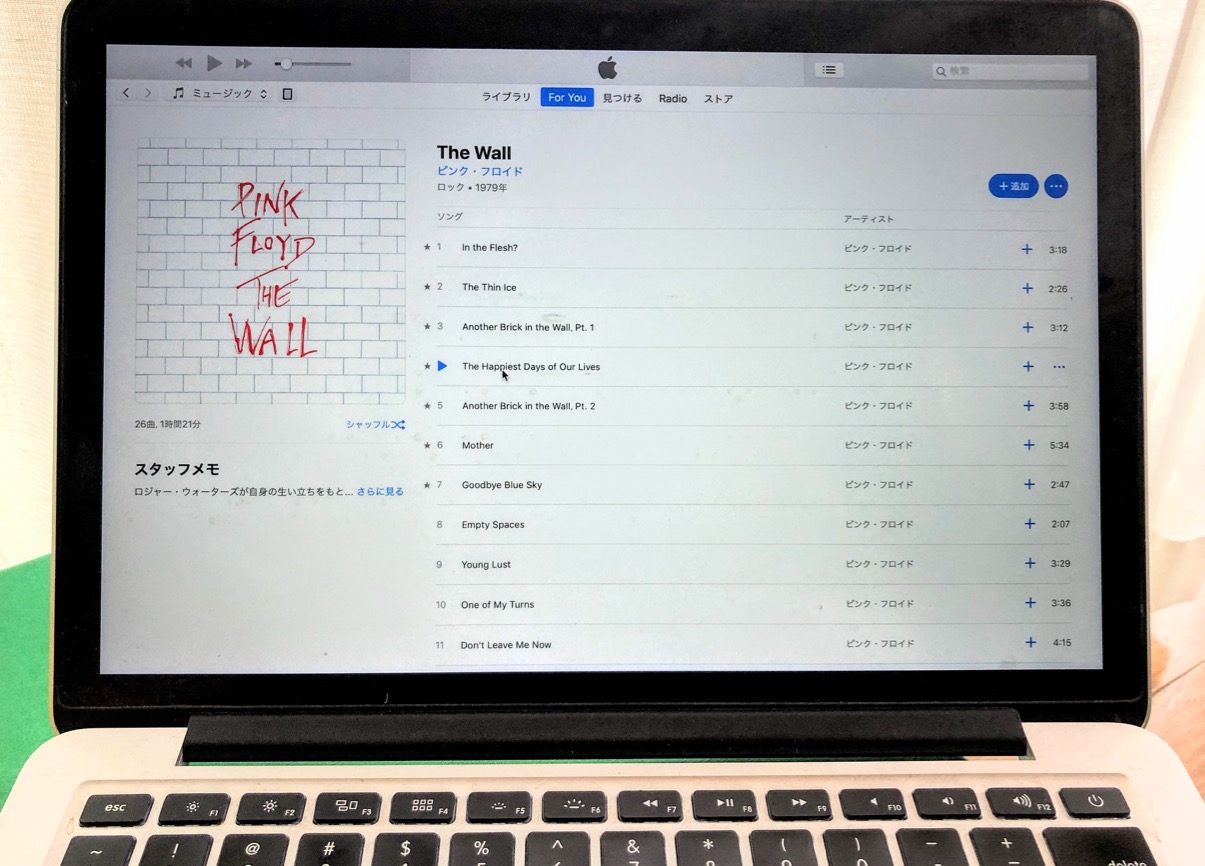
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★


