音楽MUSIC
転がる石のように名盤100枚斬り 第38回 U2 アクトン・ベイビー - U2
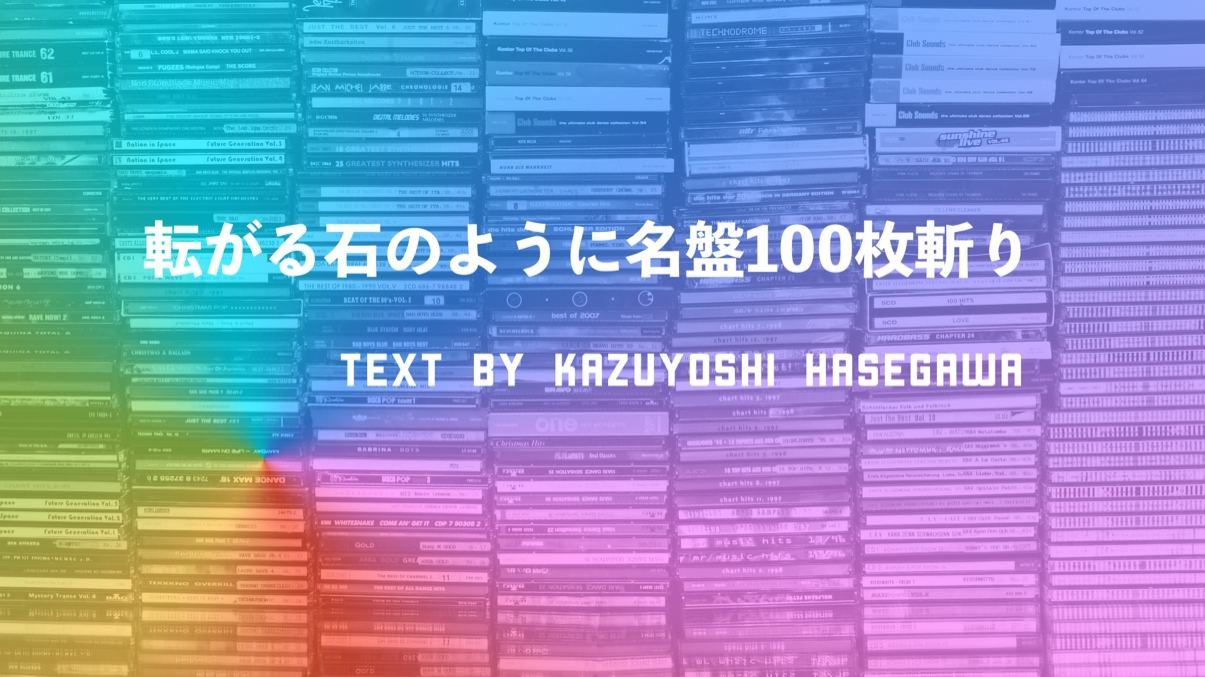
#63 Achtung Baby (1991) - U2
アクトン・ベイビー - U2
U2というバンドは昔からマジメだった。マジメで熱かった。
彼らを知ったのは、僕らがまだ中学生のころ、サード・アルバム『WAR(闘) War』で世界的にブレイクした1983年だった。アルバムは買えなかったけど、「ニュー・イヤーズ・デイ New Year’s Day」の12インチ・シングルは手に入れた。FMラジオからは「ブラディ・サンデー Sunday Bloody Sunday」が、よく流れていた。
「ニュー・イヤーズ・デイ」は、ポーランドの民主化運動、「ブラディ・サンデー」は北アイルランド問題に材を取って書かれた曲だ。
マジメすぎ。
1984年のヒット・シングル「プライド Pride (In the Name of Love)」は、黒人解放運動の指導者、マーティン・ルーサー・キングに捧げられている。熱い・・・・・・というか暑苦しい感もあったけど、ドラマティックなボノのヴォーカルを聴くと、やはり心が動く。
1987年には、「俺らの音楽にはブルースが足りん!」なんつって、アメリカに飛んでルーツ・ミュージックを研究。ブルースの大御所、BBキングとも共演を果たす。で、アメリカ・ツアーの様子と合わせて制作したドキュメンタリー映画&アルバムが『魂の叫び Ruttle and Hum』(1988年)。
どこまでもマジメ。
今回のお題は、『魂の叫び』から3年後の1991年にリリースされた『アクトン・ベイビー』だ。『ローリング・ストーンが選んだ史上最も偉大なアルバム』63位のこのアルバムを、発売当時、僕は購入していない。
思えば、リード・シングル「ザ・フライ The Fly」のPVがあかんかった。黒い革のコート着て虫みたいなサングラスかけたボノが、「ザ・フライ」という架空のポップスターに扮して、街をうろつくやつ。そして、音は、ロックというよりもダンスよりで、当時はそんな言葉知らんかったけど、インダストリアル風味。
最初、観た時には「これってマジでやってんの? それともふざけてんの?」と思ったのだった。で、その後リリースされたアルバム『アクトン・ベイビー』にも、なんとなく距離を置いてしまった。
あんなに優等生だったボノくんたちがグレてしまったのがショックだったんだろう。
そういうわけで、『アクトン・ベイビー』を初めて通して聴いたのは、AppleMusicを始めた後なので、3年くらい前のことか。U2屈指の名バラード「ワン One」を聴こうと思って検索したら、このアルバムが引っかかったのだ。
ベスト・アルバムは持っていたので「ワン」という曲は知っていたけど、『アクトン・ベイビー』に入っているという認識はなかった。
これをきっかけに『アクトン・ベイビー』を改めてちゃんと聴いてみると、ボノくんたちは、決してグレたわけではなかった。ちょっとチャラくはなったけど、根はやっぱりマジメな人たちだった。
「ダンスミュージックに大胆に接近した」と評されるアルバムだけど、いま聴くとちゃんとロックしている。当時に比べると、いまではロックにダンス・ビートを組み込むことが当たり前になったからそう感じるんだろうか?
曲はすべて練られているし、演奏も生き生きしていて、前作よりも若返ったかのような印象さえある。
そして、やはり「ワン」がすばらしい。
“僕たちは一つだ
でも、まったく同じというわけじゃなく、それぞれに個性がある
たから、お互いに認め合って、支え合わなきゃ
支え合って生きていくんだ”
世界の多様性を肯定する、この曲のメッセージは、2020年において色あせるどころか、リリース当時よりも心に迫ってくる。
「ワン」以外も、佳曲ぞろい。シングル・カットされた「ミステリアス・ウェイズ Mysterious Ways」「リアル・シング Even Better Than The Real Thing」「ワイルド・ホーセズ Who's Gonna Ride Your Wild Horses」はもちろん、「世界を抱きしめて Tryin' to Throw Your Arms Around the World」もムッチャいい曲だし、「夢の涯てまでも Until the End of the World」も味わい深い。ラストに集落されている「恋は盲目 Love Is Blindness」の鬱々とした感じもいい。
『アクトン・ベイビー』の楽曲が、前作までと比べても、まったく遜色ないと認めざるを得ない。
「ザ・フライ」はやっぱり好きになれないけど。
結局のところ、このアルバムも、U2のマジメぶりが最大限発揮された結果なんだろう。リリースの前年である1990年、東西ドイツが統一し、ソビエト連邦はこのアルバムが世に出た直後に解体した。これによって冷戦構造が終焉を迎え、「時代が変わる」という空気が世界に満ちていた頃だ。「自分たちも、前作『魂の叫び』のままでいられない!」とU2の面々はマジメに考えたのだ。
そして、ブルースやロックンロール、マーティン・ルーサー・キング、北アイルランド問題などの「歴史」ではなく、いま目の前で進行している「現代」にコミットすると覚悟を決めたんだろう。その手段として、ダンス・ビートを取り入れたと考えれば、腑に落ちる。
1989年にストーン・ローゼズがデビューし、1990年にはハッピー・マンデーズがブレイク、1991年にはプライマル・スクリームが『スクリーマデリカ Scramadelica』を世に放ち、ロックとダンス・ミュージックの接近は、イギリス音楽シーンではスタンダードとなっていた。そんな現実にU2がキャッチアップしたアルバムが『アクトン・ベイビー』だった。
「現代」にコミットするという命題は、『アクトン・ベイビー』リリース後に行われたワールド・ツアー『ZOO TV』で、より具現化する。テクノ色を強めた次のアルバム『ZOOROPA ズーロッパ』(1992年)のリリースを挟んで、世界21か国を巡ったこのツアーでは、ボノがステージ上から電話をかけるという趣向が話題を呼んだ。
政治家に直接電話をかけることもあり、フランスのミッテラン大統領、アメリカのブッシュ大統領(ジュニアの方)なんかが登場した。日本公演では政治家(当時の日本の総理は細川護熙)ではなく、当時、大相撲で横綱を張っていた曙に電話したらしい。
この試みによって、ステージと現実が地続きであることが、わかりやすく示される。
しかし、電話をかける当のボノは、例の如く、ザ・フライに扮しているのだ。結局のところ、すべては「演出」なのである。ショウの一部となることで、現実さえも消費されていく。
そんな殺伐という言葉さえ浮かぶ感覚は、U2が『魂の叫び』のリリース後に味わったものかもしれない。ホンモノになろうとアメリカに渡りルーツ・ミュージックを深堀したけど、できあがったアルバムも映画も消費されて消えていく。それがポップ・カルチャーのさだめなのだ。
そして、シーンを見渡してみると、1991年の時点でリアルだったのは、『魂の叫び』でU2が目指したホンモノの音楽ではなく、ロックとダンス・ミュージックが融合した流行のスタイルだった。
“ホンモノなんかよりずっといいよ”
『アクトン・ベイビー』の2曲目に収録されている「リアル・シング」で彼らはこう歌っている。このサビについては、「ホンモノの愛なんかより束の間のアヴァンチュールの方がよほどいい」というのが、一般的な解釈だけど、上のようなことを考えると、1991年の世界に対する皮肉のようにも響く。
そんな世界に真っ向から向き合うには、求道者のイメージを引きずるボノ自身のままでは、難しかった。そこで産まれたのがザ・フライというオルター・エゴだったというわけか。
やっぱり、U2は、マジメ。
これ以降も、そのキマジメさゆえに、U2は右往左往することになるんだけど、その道程も、いま振り返ると、胸に迫るものがある。『アクトン・ベイビー』は、その出発点。同時代に聴いとくべきアルバムであった(反省)。
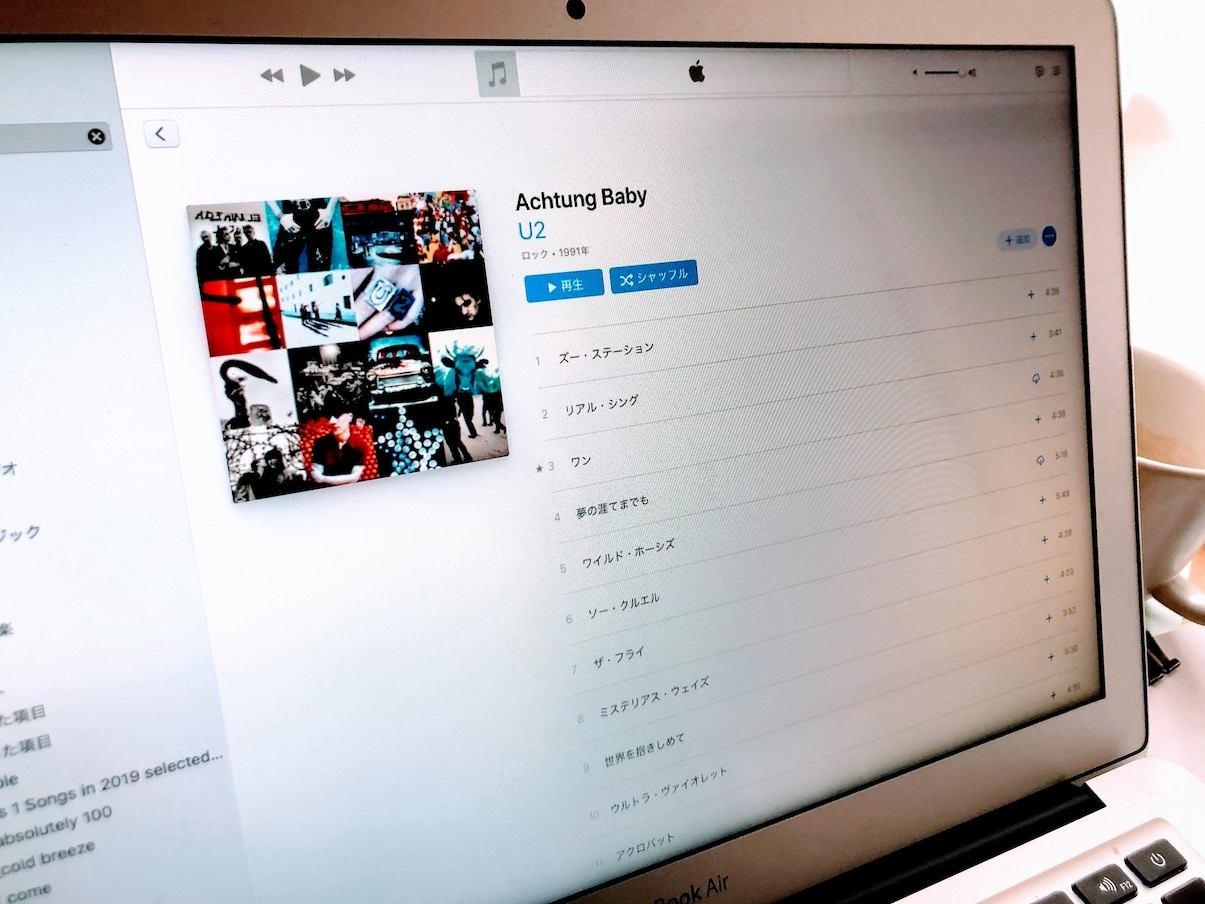
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★


