音楽MUSIC
転がる石のように名盤100枚斬り 第52回 #49 At Fillmore East (1971) - THE ALLMAN BROTHERS BAND 『フィルモア・イースト・ライヴ』 - オールマン・ブラザーズ・バンド
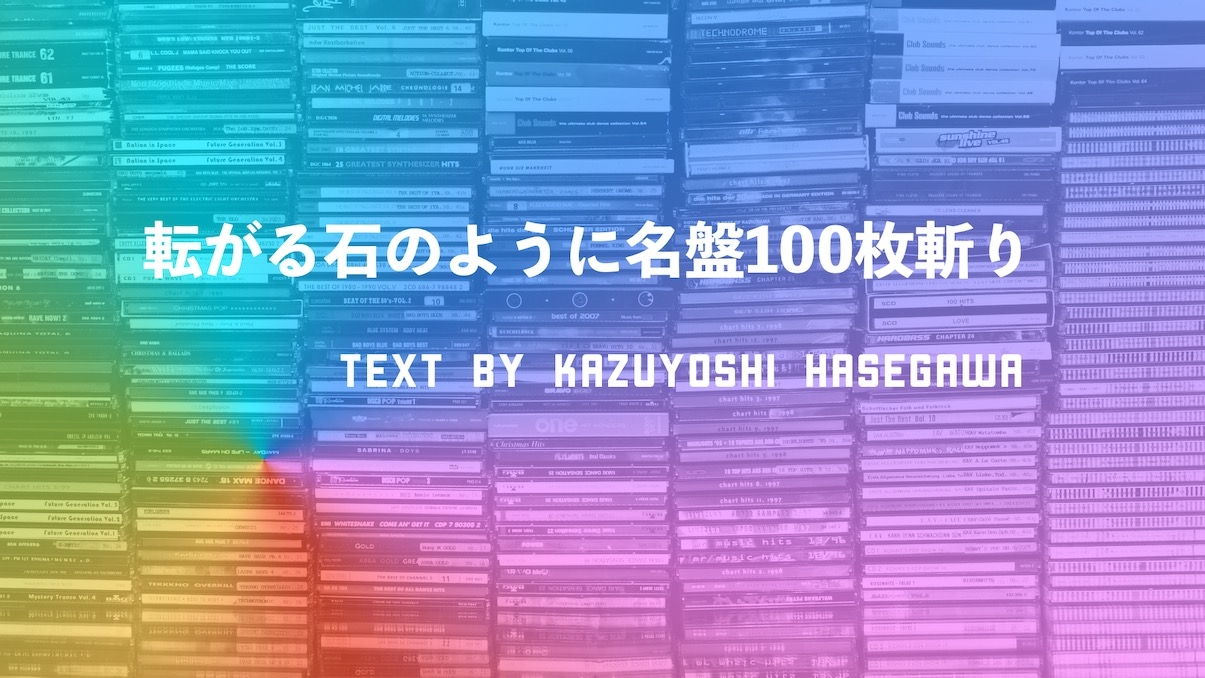
大江千里が、「だから僕はポップスを手放した」というコラムを、『ニューズウイーク日本版』(WEB版5月29日公開/本誌5月25日号掲載)に寄稿していた。
大江千里という人は、1980年代に一世を風靡したポップ・シンガーですね。ソニーが出版していた雑誌『PATi PATi』によく出ていたイメージだけど、僕はこの人のことは、よく知らない。
よく考えたら、『PATi PATi』、買ったことないし。
代表曲も知らないくらい、大江千里とは縁がなかったけど、彼が日本を離れ、アメリカでジャズ・ピアニストとして活動しているという話は、なんかの報道で知っていたので、コラムにも目を通してみた。
その内容は、タイトル通り。
ポップスから離れた理由を要約すると、大人になって色々とリアルに経験を重ねた結果、「ポップスに特有のキラキラした短い物語」を紡ぐことが難しくなったからということらしい。
「ポップスはキラキラしてないとダメ」「ポップスはリアルな感情を読み込むものではない」っていう思い込みは、日本のポップスと大江自身の限界を指し示しているだけのような気がする。
海外のポップスはより多様だし、どんどん進化しているもんね。
この「キラキラしてないとダメ」という思い込みが呪詛のようにまとわりついているから、日本のポップスはラヴ・ソングばっかなんだろうなぁと思ったけど、まぁ、いい。この話は置いておこう。
おもしろいなぁと思ったのは、大江がなんでジャズの道を選んだのかという点。
曰く、ジャズの世界、「それは3分間の咀嚼の世界ではなく、この瞬間に即興的に生まれる喜怒哀楽が詰まった世界なのだと思う。」
即興演奏、いわゆるインプロヴィゼーションってやつは、ジャズの醍醐味だ。インプロがバリバリのポップスは、確かにない。そんなん、3分じゃ終わらないし。
大江は即興性を、自分の言葉にならない感情をダイレクトに表出するものとして捉えている。「言葉にならない」って部分が、すごく重要だったんだろうなぁ。
より根源的でプリミティヴな感情を解き放つために、大江にはジャズが必要だったということで、それは非常によく理解できた。
ローリング・ストーン誌が選ぶ『史上最も偉大なアルバム』49位はサザン・ロックの名盤『フィルモア・イースト・ライヴ』。そのハイライトは、即興演奏、インプロヴィゼーションが炸裂する13分04秒の大作「エリザベス・リードの追憶 In Memory of Elizabeth Reed」である。
僕は長い曲が苦手だ。だから、プログレッシヴ・ロック聴かんのよ。
でも、オールマン・ブラザーズ・バンドは聴くんだなぁ。
だって、オールマン・ブラザーズ・バンドの長尺の曲は、気持ちがいいのだもの。聴いているうちに陶然としてくる。このままずっと演奏しててくださいとか思う。
このアルバムのリリース直後、バイク事故で命を落とし伝説となった、リード・ギタリスト、デュアン・オールマンのあだ名は、「スカイドッグ」っていうんだけど、その由来は、その演奏が「空」へと駆け上るようだったことと、デュアンが犬に似ていたことだそうだ。うん、似てる。
「エリザベス・リード~」前半部分でのデュアンの演奏は、「スカイドッグ」の異名にふさわしい。ギターの音色が大空へ舞い上がる。そして、後半は、インプロヴィゼーション100%。バンド・メンバーの真剣勝負に、思わず引き込まれる。
「エリザベス・リード~」の作者は、もう一人のギタリスト、ディッキー・ベッツだ。マイルス・デイヴィスの1959年の傑作『カインド・オブ・ブルー Kind of Blue』に収録されている「オール・ブルース All Blues」に影響を受けたことを、ベッツ自身が認めている。
ジャズの影響を受けているからって、大江千里がコラムで言う「この瞬間に即興的に生まれる喜怒哀楽が詰まった世界」が現れるかというと、ちょっと違う。
根本にあるのが、「言葉にならない」根源的な感情であることは共通するけど、「喜怒哀楽」というよりも、ステージでオーディエンスを前に演奏することの興奮が前面に出ている。あふれ出るのは、ウエットな「感情」ではなく、純粋に音楽的な喜び。
『フィルモア・イースト・ライヴ』収録曲のうち、前半4曲はブルース・ナンバーのカヴァーで、なかでも初っぱなの3曲は、あくまでも主役は、ツイン・ギター、特にデュアンのスライド・ギターだ。
「ステイツボロ・ブルース Statesboro Blues」のオリジナルは、スライド・ギターの名手ブラインド・ウイリー・マクテルによる曲。
「誰かが悪かったのさ Done Somebody Wrong」は、 これまたスライド・ギターで名を馳せた、エルモア・ジェームスの手によるスタンダード・ナンバー。
ジャジーなオルガンも印象的な「ストーミー・マンデイ Stormy Monday」の作者は、「モダン・ブルース・ギターの父」、T・ボーン・ウォーカーだ。
ブルース・ギターの巨人のナンバーが並んでいるのも、意図があってのことだろう。
ところが、4曲目の「ユー・ドント・ラヴ・ミー You Don't Love Me」になると、勝手が違ってくる。オリジナルはブルース・シンガー、ウイリー・コブズによる1961年のヒット。
ここでバンドのインプロ魂が一気に燃え上がる。
粋な旋律のリフに、デュアンのスライド・ギター、グレッグ・オールマンのオルガンやトム・ドゥーセットのハーモニカが入れ替わりでかぶさって、徐々に緊張感が増していく。
6分を経過したあたりで、クール・ダウンしてくるので、「そろそろ終わりかなぁ」なんて思うが、ここからが本番。
ギター・ソロに合わせてドラムが切り込んでくる。ギターも段々と熱さを増してくる。
この後は、延々と即興演奏が続くんだけど、退屈することはない。音の渦に巻き込まれていく感じで、ただ耳を澄ませるのみ。
アナログ・レコードのB面全部を使って収録したこの曲の長さは、19分15秒。
この曲以降は、怒涛のインプロ攻勢。
「アトランタの暑い日 Hot 'Lanta」は、5分17秒という尺の短さを侮ってはいけない。頭からお尻までインプロヴィゼーション。ギターが効いてるけど、ジャズっぽさも感じる。
そして、「エリザベス・リード~」で、前述通り、神がかった演奏を披露した後は、ラストの「ウィッピング・ポスト Whipping Post」で再びドラマティックな即興を繰り広げる。
後半の、泣きのギターからカオスに突入していく感じは黙示録的。収録時間はアルバム最長の23分03秒。
「ユー・ドント・ラヴ・ミー」後半から、ずっと緊張感が持続。聴き終えるとグッタリしてしまうほど、密度の濃い演奏が刻み込まれている。
一般的には、サザン・ロックには泥臭いというイメージがあるけど、『フィルモア・イースト・ライヴ』で聴けるのが、垢抜けて洗練された演奏だ。
これって、やっぱり、デュアンのギター・スタイルによるところが大きいんだろうな。彼のスライド・ギターからは、都会的なにおいを感じる。
オールマン・ブラザーズ・バンド結成前に、スタジオ・ミュージシャンとして、ウィルソン・ピケットやアレサ・フランクリンなど、錚々たるサザン・ソウル・シンガーのバックを務めた経験が反映しているのかもしれない。
デュアンの死後に制作された『ブラザーズ&シスターズ Brothers and Sisters』(1973年)では、ディッキー・ベッツがメインでギターを担当していて、ファンキーな仕上がりだけど、垢抜けたタッチは失われている。
「都会的で洗練されたサザン・ロック」は、デュアンなくしては成り立たないのだった。
『フィルモア・イースト・ライヴ』に収められた、1971年3月12~13日のステージは、1992年以降、収録曲を追加し、数ヴァージョンがリリースされている。
僕は、2003年にリリースされた「デラックス・エディション」を持っている。オリジナルの収録曲が7曲なのに対して、全13曲のCD 2枚組。さすが、「デラックス」。
ちなみに、2014年リリースの『1971 フィルモア・イースト・レコーディングス』は、ライヴを完全収録したもので、CD6枚組、収録時間6時間5分21秒。これを聴くのは根性いりますね。
収録曲数だけではなく、曲順も異なるので、聴き比べるのもまた一興(時間があれば)。
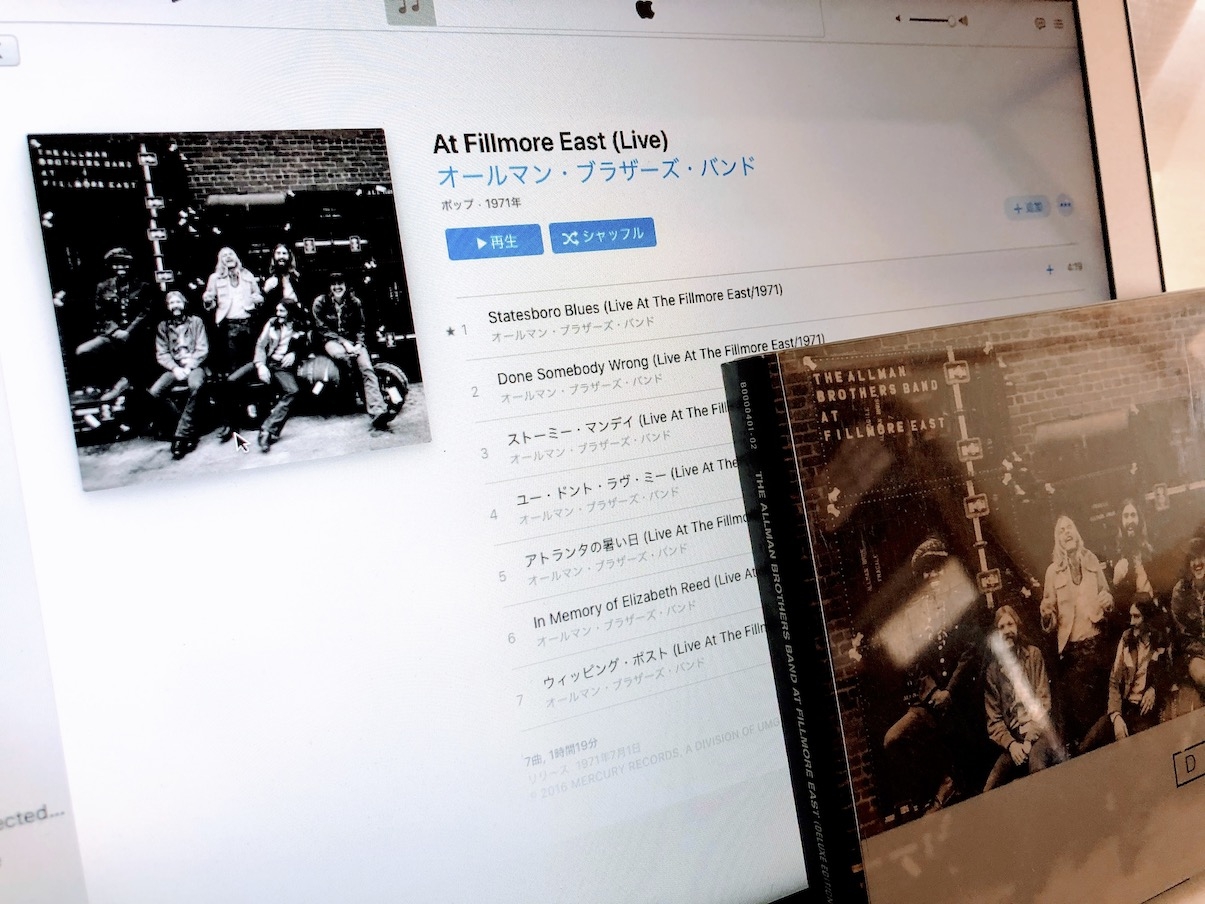
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★


