音楽MUSIC
転がる石のように名盤100枚斬り 第59回 #42 The Doors (1967) - THE DOORS 『ハートに火をつけて』 - ザ・ドアーズ

ここのところ、少々バタバタしており、この連載の更新も滞っていたところに、恐れていた事態が発生してしまった。
この連載の元ネタである『ローリングストーンが選ぶ史上最も偉大なアルバム』の最新版が発表されてしまったのだ。ちなみに、ここで今まで紹介してきたランキングは、2003年に発表されたものをベースに2012年にアップデイトされたもの。それが、17年ぶりに新たな指標でランキングし直しされたことになる。
そろそろかなぁとは思っていたんだけど、あと、1年、いや半年待ってほしかった。
ざっと、100位以内を見てみると、以前のランキングとはかなりの変動がある。『ロッキン・オン』WEB版によると「全体としては、500位以内に154組の新しいアーティスト、アルバムが入った」そうです。
ヒップホップ/ラップ勢の隆盛とザ・ビートルズの凋落は予測できたことだけど、トップ3に選ばれたアルバムは、予想外だった。今の若者にも届く音ということでセレクトされているんだろうけど、いろいろと物議を醸しそうなランキングではある。
さて、この連載、どうしましょうかね。今更、新ランキングを元に100位から改めてカウントダウンするってのは、さすがにツラい。とりあえずは、残っている2003年度版『史上最も偉大なアルバム』の残り42枚を紹介しつつ、最新ランキングでどのように位置付けられたのかも検証していこうと思う。
で、今回のお題、『ローリングストーンが選ぶ史上最も偉大なアルバム(2003/2012)』42位にランクインしたのは、ザ・ドアーズのデビュー盤『ハートに火をつけて』なわけだけど、『史上最も偉大なアルバム』最新版で順位を確認したところ、なんと86位に大幅ダウン。
ロック史に残る一枚ではあるけど、2020年代の音楽シーンに及ぼす影響力は、すでに大きくはないということか。
やっぱ、ドアーズとか、今の若者には古臭く響くんだろうな。僕がこの『ハートに火をつけて』を手にしたのは、大学生の時だと思うけど、その時も「ザ・60年代って感じやねぇ」と思ったもんなぁ。
今回、久々に聴いてみて「ザ・60年代」感の正体がわかった。「水晶の船 Crystal Ships」「20世紀の狐 Twentieth Century Fox」「君を見つめて I Looked at You」「チャンスはつかめ Take it as it Comes」あたりの曲に漂う、日本のグループ・サウンズ(GS)感だ。
GSの真髄は、ロックと歌謡曲のハイブリッドだ。上記の曲はどれもオルガンが効いていて、ロックとしての強度はあるんだけど、どこかウエットでメロディアス。まさにGS好みの音やん。
つまり、このスタイルは、60年代ロック・シーンの共通言語の一つだったってことかもしれない。
加えて、ジム・モリソンの芝居がかったヴォーカルも時代を感じさせる。ベルトルト・ブレヒト&クルト・ヴァイルのオペラ曲をカヴァーした「アラバマ・ソング Whisky bar(Alabama Song)」は、まんまヴォードビル・ショーだし、「エンド・オブ・ザ・ナイト End of the Night」のもったいぶった感じも芝居臭い。
とは言え、トップ100に入るロックの名盤、収録曲には時代を越えたカッコよさもある。「ブレイク・オン・スルー Break on Through (To the Other Side)」は、ファンキーでクールな手触りだし、「ソウル・キッチン Soul Kitchen」は、さりげないけど粋な印象を残す一曲。
ドアーズの代名詞とも言える「ハートに火をつけて Light My Fire」は、超絶ポップな傑作で、狂ったように鳴り響く乾いたオルガンを聴くと、やっぱり高揚してしまう。
アルバムのハイライトは、ひときわダークな印象を与える、ラストの「ジ・エンド The End」だろう。静謐な曲調は美しいと言ってもいいくらいだけど、聴いているとなぜか鬱な気分になる。
一般的に、この曲のエディプスコンプレクスを題材にしてるとされているけど、ジム・モリソンが文学的な素養を披露しつつ、実の両親に嫌がらせをしたというだけで、決して主題ではない。
じゃぁ、ジム・モリソンによる文学的な歌詞が何を表現しているのかと問われると、正直言ってわからん。文学的すぎるのよ。でも、とにかく「もう終わり」だってことはわかる。
ここで行き止まり。出口なし。
フランシス・フォード・コッポラ監督が、問題作『地獄の黙示録』(1979年)の劇中で流したのも納得の絶望感。
デビュー・アルバムにこんな曲をぶっ込んでくるバンドは、未だにいないんじゃないか。
アルバムを通して聴くと、少々古臭さは感じるにしろ、佳曲揃いだし、もっとザ・ドアーズのこと評価してもよかったじゃない、30年前の俺?とも思ったけど、何回か聴くと、ジム・モリソンの存在が鼻についてくる。
モリソンは、稀代のロック・カリスマだし、モリソンあってのザ・ドアーズであることは、モリソン死後のバンドの顛末を見れば明らかなんだけど、そのカリスマぶりがわざとらしいのよね。
よく目にするモリソンのポートレイトは、だいたい上半身裸でボトムはピッタリとした革のパンツ。セックス・アピールとしては、あまりにわかりやすい。1960年代末期にはセンセーショナルに受け止められたかもしれないけど、今見ると少々滑稽だ。
ジム・モリソンと言えば、ステージでマスターベーションをしたとして逮捕、有罪判決を受けたことが有名だけど、実は、イチモツを実際に開陳したわけではなく、パンツから肌色の下着を引っ張り出して、自慰するマネをしただけという説もある。真偽は不明だけど、ジム・モリソンだったらやりかねんなぁと思った。
つまり、ジム・モリソンは、「ロック・スター、ジム・モリソン」を演じていただけではないかということだ。
文学的な才能に恵まれ、社会通念に縛られることなく奔放に振る舞い、マイクを握ればワイルドなアクションと、魔術的な響きを持った歌声で観衆を魅了するロック・スター。一方で、その繊細さゆえに、ドラッグやアルコールに溺れていく破滅型の天才。
そんなパブリック・イメージと等身大のジム・モリソンは、かなり乖離してたんじゃないかな。モリソンがロック史上でも稀なカリスマ性を備えていたことは否定しないし、実際いろいろな面で才能があったことは認めるけど、彼が書く詞も、歌声も、その人生も、すべてができすぎで、作り物のように思えてしまう。
上述した「ジ・エンド」が象徴的だ。モリソンの手による詞には、さまざまなギミックが効いているけど、メッセージと呼べるようなものはなく、実体のない「文学的な絶望感」だけが、誰かが吐き出したタバコの煙みたいに、ただ漂っている感じ。
そもそも「カリスマ」なんてものは、周囲の幻想を体現するだけの存在で、中身が空っぽだからカリスマたりえるのかもしれんけど。
ジム・モリソンは、『ハートに火をつけて』で世界中でセンセーションを巻き起こした4年後の1971年、滞在先のパリで命を落とす。この頃のモリソンは、セックス・シンボル時代の面影はなく丸々太っていたそうだ。
そんな体型で「ジム・モリソン」を演じることはできなかった。だから、自らで死を選んだんじゃないだろうか。
公の死因は「心臓発作」となっているけど、実際にはヘロインのオーヴァードースだったという見解が優勢みたいだし。
ある意味、「ジム・モリソン」を生ききったうえの結末と言えるかもしれない。
結局、あまり褒めてないような気もするけど、『ハートに火をつけて』は聞き応えのある傑作だと思う。ジム・モリソンのヴォーカルがまき散らす不穏な空気感は唯一無二だろう。
少なくとも、86位というポジションは低すぎる。そんな抗議の意味も込めて・・・・・・。
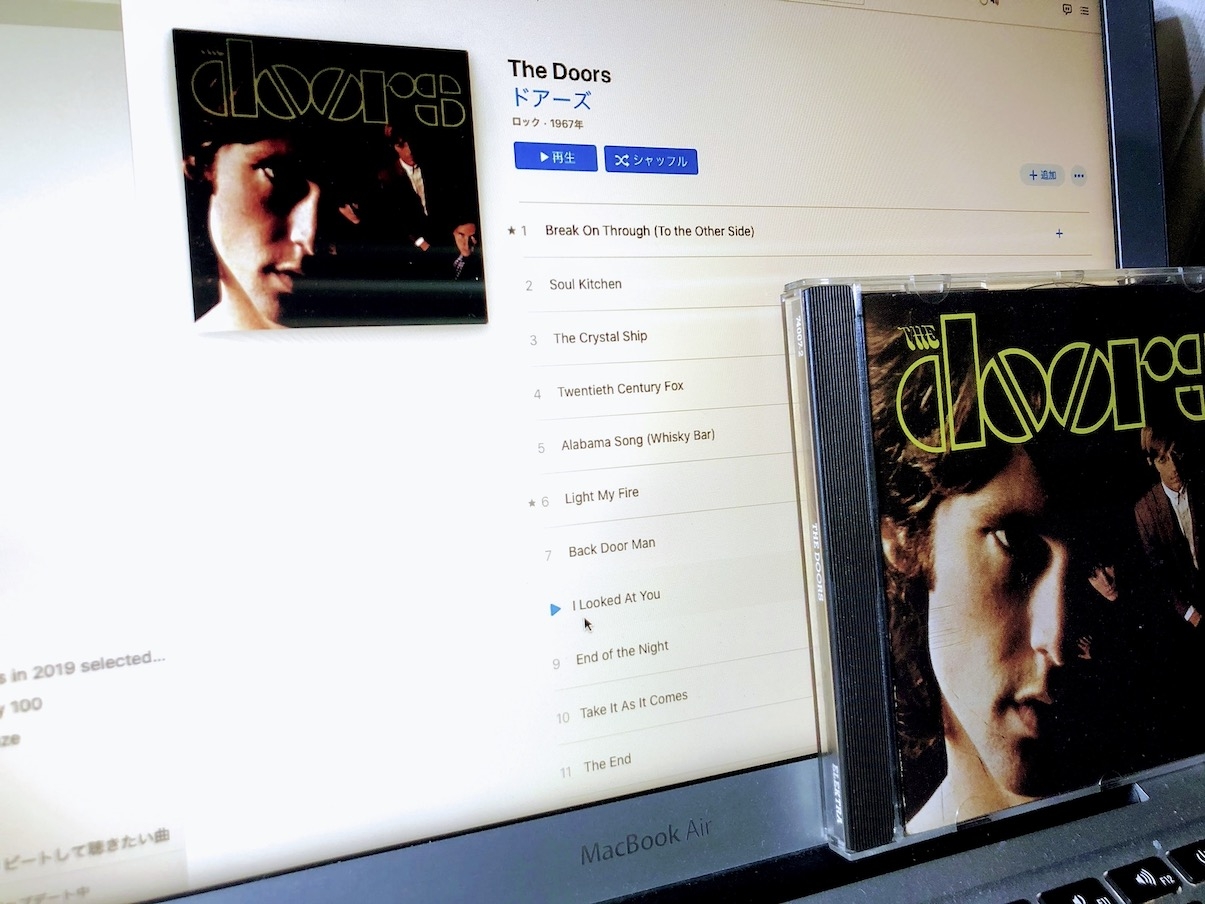
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★


