音楽MUSIC
転がる石のように名盤100枚斬り 第63回#38 The Anthology (2001) - MUDDY WATERS 『アンソロジー』 - マディ・ウォーターズ
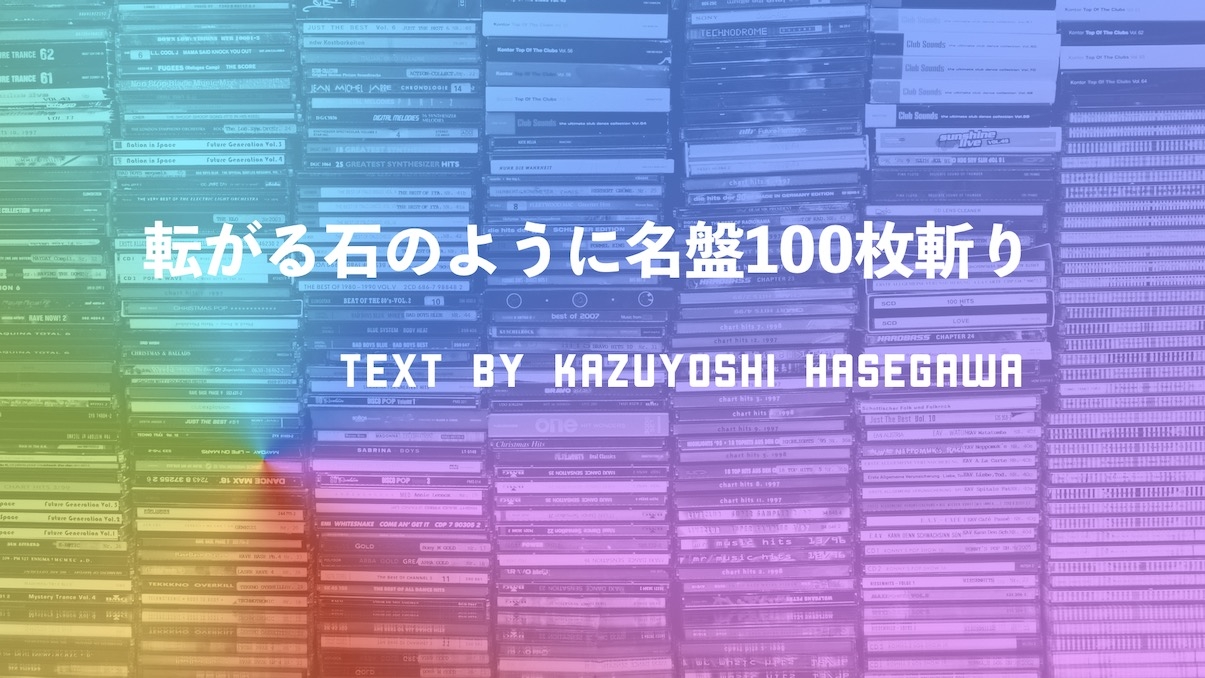
マディ・ウォーターズのおばあちゃんって、どんな人だったんだろう。
「マディ」というのは実は愛称で、彼が泥(mud)にまみれ、嬉々として遊んでいる様子を見て、おばあちゃんが付けたらしい。本名はマッキンリー・モーガンフィールド。覚えにくいし、あまりかわいくない。
マディが生まれたのは1913年だから、おばあちゃんは1870年代の生まれだろうか。アメリカで南北戦争が終結した直後ということか。北軍の勝利により、黒人たちは奴隷の身分から解放されたものの、マディが育ったミシシッピ州では揺れ戻しも大きく、依然、苛烈な黒人差別が続いていたようだ。
だから、決して楽な暮らしではなかったんだろうけど、おばあちゃんは、いわば南北戦争における「戦後生まれ」で、それまでの黒人にはなかった新しい感性を持っていたんじゃないか。
「泥水で遊ぶのが好きだからマディ」なんて思い付くくらいだから、明るくて愛嬌のあるおばあちゃんだったんだと思う。
その楽観的で前向きな感性は、マディにも受け継がれたんじゃないだろうか。
なんてことをツラツラと考えたのも、「マディ・ウォーターズ」が本名じゃないって、さっき知ったからなのでした! というか、芸名か本名かなんて、考えたことなかった。
これまで縁遠いミュージシャンだったのだ。
もちろん、ブルースの巨人としての名声は認識していたし、「ザ・ローリング・ストーンズ」というバンド名、そして「ローリング・ストーン」という雑誌名が、その代表曲「ローリング・ストーン Rollin’ Stone」に由来すること、さらに同曲が、ボブ・ディランにインスピレーションを与えたことも、知ってはいた。
この連載のタイトルも元をたどれば、この曲ってことになる。
あと、アルバム・ジャケットで彼のポートレイトを目にする機会は結構あって、堂々としているけどどこか優しげな容姿に、「良い顔したおじさんだなぁ」とは常々思っていた。
振り返ってみると、マディ・ウォーターズを敬遠していたというわけではなく、単純に聴く機会がなかったということなんだけど、あと、歳とってからブルースの名盤に手を出すのは、「いかにも」な感じがして、食指が動かなかったというのはあるかもしれない。五十路に入ったからといって、わかったふうな顔をしてブルースを聴くのは、今もちょっと気恥ずかしい。
『史上最も偉大なアルバム』2003発表・2012改訂版38位は、マディの編集盤。これをいい機会に、AppleMusicで聴いてみた。
このアルバムは、年代ごとにまとめられていた複数のベスト盤を、CD2枚にパッケージしたという代物で、一番古い音源は1947年のもの。一番新しいやつで1972年録音。マディ・ウォーターズの四半世紀分の活動を網羅していることになる。
それ以降の音源が収録されていないのは、所属レーベルが変わったからだろう。
1947年に録音されたデビュー曲「ジプシー・ウーマン Gypsy Woman」から順に聴いていくと、アコースティックでシンプルな演奏の「デルタ・ブルース」が、エレクトリック・ギターをフィーチャーしたバンド・サウンド「シカゴ・ブルース」へと発展していく過程がよくわかる。
つまり彼の音楽は、ブルースとロックンロールをつなぐピースとして評価されているってことなんだろう。
アルバムの序盤は、ヴォーカルとスライド・ギターが生々しく響く、いかにもな感じのブルース・チューンが並んでいるが、「Stuff You Gotta Watch」あたりになると、バンド・アンサンブルで聴かせるスタイルになっていて、かなりロックンロールに接近している。
後年、様々なアーティストがカヴァーする「Hoochie Coochie Man」なんかは、モロにブルース・ロックという趣き。かと思えば「Diamonds at Your Feet」ジャズぽい要素もあっておしゃれ。
ここに収められた50曲は、当たり前の話だけど、どこを切ってもブルース。収録時間147分。聴いているうちに飽きるんじゃないかと思ったけど、曲調にヴァリエーションがあるので意外にイケる。
60年代の曲が並ぶアルバム後半は、マディのヴォーカルもギターも円熟の域に達していて余裕綽々。ドキドキするようなスリルはないけど、懐の深い音というか、ギターとヴォーカルの響きがじんわり心に来る。
「Look What You've Done」とか「Close to You」とか「I Feel So Good」とか、なんてことないオーソドックスなブルースなんだけど、ついつい聴き入ってしまうのだった。
あぁ、こんなにブルースが心地いいなんて、なんだか自分の加齢ぶりを感じる。
アルバム全体の印象としては、レイドバックしていて、天気のいい休日に酒を片手にのんびり聴くのにぴったりって感じだけど、唯一異彩を放っているのが、やっぱり「ローリング・ストーン」だったりする。
この曲の元ネタは、1920年代にレコーディングされたブルース「カンサス・シティ・ブルース Kansas City Blues」、それをさらに改変した1941年の「キャットフィッシュ・ブルース Catfish Blues」だそうな。
「ローリング・ストーン」というタイトルにしたマディ、冴えてる。
これは、「A rolling stone gathers no moss. (転がる石に苔は生えない)」というイギリスの諺から引っ張ってきている。
諺自体の解釈も二通りあって、「rolling stone」という言葉を、「風来坊」「根なし草」というネガティヴな意味にとるか、「常に自分をアップデイトする人」というポジティヴな意味にとるかで違ってくる。
マディが歌ったのはどちらの意味だろうか?
少なくともボブ・ディランが「ライク・ア・ローリング・ストーン Like a Roklling Stone」(1965年)で聴かせたような楽天的な響きは、ここにはない。
つぶやくように、もしくは何かを嘆くように歌うマディの深みのある声に、スライド・ギターの音色が絡みつく。
前半のパートで歌われているのは、人妻との情事で、「ついさっき、旦那は出かけたばかりよ」なんてセリフで誘惑されるマディ。
「rollin’ stone」というフレーズが出てくるのは、次のパートだ。
“おふくろが親父に言ったらしい
俺が生まれる前のことさ
「どうも男の子をみごもっちゃったみたい
思うんだけど、この子はさぁ、この子はさぁ、
きっと風来坊(rollin’ stone)になるような気がする
きっとそう、根なし草の風来坊・・・・・・”
で、この主人公が「転がる石」のごとく自由な生き方をしているかと言うと、そうではない。最後のパートで、マディはこう繰り返す。
“そろそろ元いた場所に戻んなきゃ”
「根なし草」どころか、がっしり根を張った生活じゃないか。
「転がる石のように自由に生きたい」なんて言っても、現実にはそんなに簡単な話ではなく、生きていくためには、妥協も必要だし、しがらみに絡みとられて身動きできないことも多い。
公民権も認められていない1940~1950年代の黒人なら、なおさらだろう。
結局、「ローリング・ストーン」は、風来坊にもなれず、変わり映えしない毎日を生きるしかない男の絶望感を歌った曲かもしれない。
実際のマディ・ウォーターズはどうかと言うと、生まれ故郷のミシシッピには戻らず、イリノイで音楽人生を全うした。
後年、ザ・バンドの解散ライヴ『ラスト・ワルツ』(1976年)に参加。さらに1977年以降は、白人にもかかわらずマディが「俺の義理の息子」と呼んでいたジョニー・ウインターのサポートも得て、1983年に亡くなる直前まで精力的に活動した。
このコンピレーションでも十分に表現されているように、マディは「常に自分をアップデイト」し、新しいブルースを追い求めた。そういう意味では、マディは「rolling’ stone」という言葉のポジティヴな側面を体現する存在と言える。
いくつになっても、日々新鮮に「転がる石」のように生きていけるといいなぁ。マディの溌剌とした歌声を聴きながら、頭の中が苔むしつつある僕なんかは、しみじみと思ってしまった。
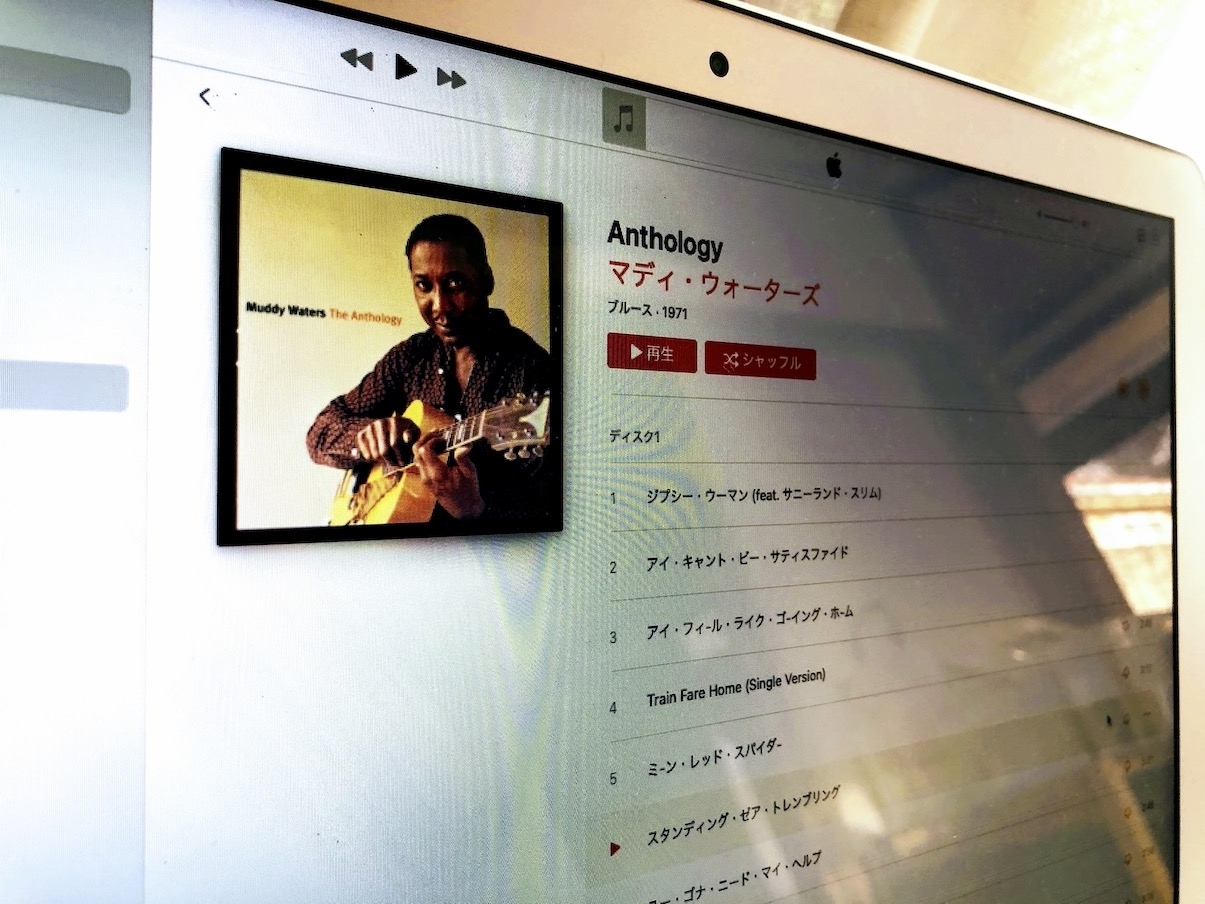
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★


