音楽MUSIC
転がる石のように名盤100枚斬り 第65回#36 Tapestry (1971) - CAROL KING 『つづれおり』 - キャロル・キング
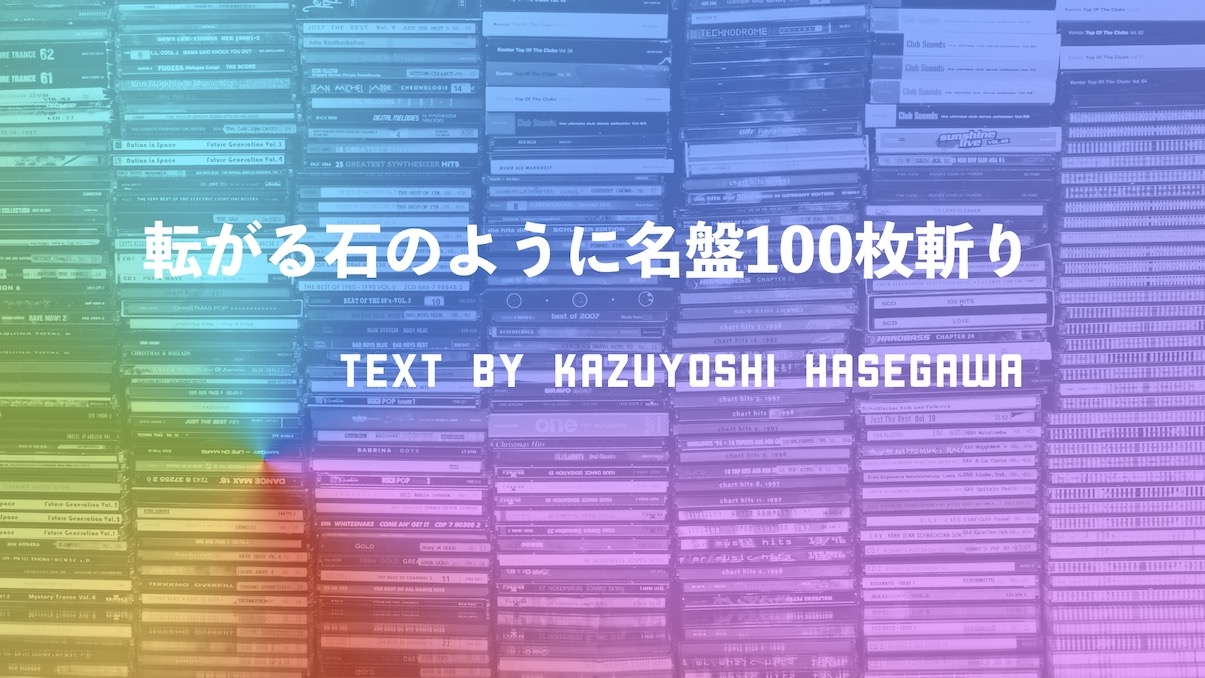
前回採り上げたイーグルス『ホテル・カリフォルニア』のタイトル・トラックの歌詞で、”そのスピリットは1969年から切らしているんです”という有名な一節がある。
「スピリット(spirit)」という言葉は、「蒸留酒」と「精神」のダブル・ミーニングだと解釈されていて、ロックで世界が変わるという無垢で理想主義的な希望は、1969年に潰えたという意味らしい。
うまいこと言うね。
1969年といえば、8月にウッドストック・フェスティバルが「愛と平和の祭典」として成功を収める一方で、12月にはザ・ローリング・ストーンズのライヴ中にオーディエンスが刺殺されるという「オルタモントの悲劇」が起こり、「ロックンロールにとって最悪の日」と報道された。
明けて1970年4月にはザ・ビートルズが実質的に解散。9月にはジミ・ヘンドリクスが、10月にはジャニス・ジョプリンが、ドラッグにより相次いで命を落とす。
こうやって列挙すると、確かに何かが終わった感がある。
「愛と平和」とか「連帯」なんて言葉が空疎に響くようになった、そんな1970年代初頭、ロックに変わって、アメリカ・ミュージック・シーンのメイン・ストリームに躍り出たのが、シンガー・ソングライター(SSW)と呼ばれるアーティストたちだった。
彼らは、徒党を組んで、実現するはずもない理想を追い求めるのではなく、個人として自律し、現実と真摯に対峙した。
クスリで死んじゃう人もいないし、60年代のアーティストよりもずいぶんとマジメなのだ。
この時期にアメリカでリリースされたSSWの名盤は数あれど、ニール・ヤングの『アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ』(1970年・本連載第27回でレヴュー済)、ジョニ・ミッチェルの『ブルー』(1971年)、そして、今回のお題、『ローリングストーン誌が選ぶ史上最も偉大なアルバム』2003発表・2012改訂版36位にランク・インしたキャロル・キングの『つづれおり』の3枚は、間違いなく僕のオールタイム・ベストのトップ40に入る大事なアルバムだ。
なかでも『つづれおり』は一番とっつきやすくて万人受けするんじゃないか。頭から尻尾まで名曲だらけ。時代を経てもみずみずしさを失わない名盤中の名盤。間違いなく後世に残る傑作アルバム。聴くべし。
・・・・・・と、ここまで絶賛しておいてなんだけど、キャロル・キングというアーティストには、ニール・ヤングやジョニ・ミッチェルに対するほどの思い入れは、僕にはない。彼女に対しては、なんか「違和感」がつきまとうんだな。
1960年代、キャロル・キングが当時の夫であるジェリー・ゴフィンとソングライティング・チームを組んで、ニューヨークのブリル・ビルディングを拠点に数々のヒット曲を手がけたことは、広く知られている。
そのほとんどは懐メロで、僕にはなじみがない曲が多いんだけど、誰もが知る名曲中の名曲、リトル・エヴァの「ロコ・モーション The Loco-Motion」が、この二人の手によるものだと知った時は、ビックリした。
さらに驚いたのは、ザ・ビートルズがファースト・アルバムでカヴァーした「チェインズ Chains」は、二人が書いてクッキーズがヒットさせた曲だったという事実。
ちなみに、「ロコ・モーション」は1962年のヒットで、クッキーズが「チェインズ」を全米チャートのトップ20に送り込んだのも、同じく1962年のこと。
1971年に『つづれおり』を発表した時、キャロル・キングは何歳だったのよ? 40歳くらい?・・・・・・と一瞬混乱してしまうけど、1942年生まれだから、29歳になったばかりだった。
調べてみると、1958年、16歳の時、自作曲で歌手デビューを飾るという早熟ぶり。その直後、進学したカレッジでジェリー・ゴフィンと出会い一目惚れ。妊娠、結婚、ソングライティング・チーム結成という急展開。この時、キャロル・キングはまだ17歳か18歳か。
そして、1960年、19歳の時、黒人ガールズ・グループ、シュレルズに提供した「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー Will You Love Me Tomorrow」が全米ナンバーワンとなり、売れっ子ソングライターとなるのだった。
幼い頃から相対音感を持っていたってんだから、天才の部類に入るんだろうなぁ。『つづれおり』の頃には、プロのソングライターとしてのキャリアは、すでに13年を数えるわけで、円熟の境地の達していたと見ていい。
それにしても、『つづれおり』でのいかにもSSW然とした素朴そうな佇まいと、「ロコ・モーション」に代表される1960年代の職業作曲家としての華やかなキャリアが、うまく噛み合わない。こういうところが「違和感」を生んでいるのかもしれない。
1967年、キング&ゴフィンが書いた「ゴーイング・バック Goin’ Back」を、フォーク・ロックでブレイクしたバーズが録音することになった時、メンバーのデイヴィッド・クロスビーは、「あんなん工場でつくる製品とおんなじで魂こもってないやろ」(かなり意訳)とレコーディングへの参加を拒否している。
デイヴィッド・クロスビーの気持ちはわかる。ブリル・ビルディングのソングライターってロックからもっとも遠い存在だもんね。
さらに言うと、キャロル・キングへの「違和感」はこれだけじゃないんだな。彼女のキャリアを俯瞰するたびに、いったい彼女の自己表現欲求はどこを向いていたんだろうという疑問が頭に浮かぶのだ。
キャロル・キングは、自分の歌に自信がなく、ソロ活動に積極的になれなかったけど、盟友、ジェイムス・テイラーの励ましによって、シンガーとしても表舞台に立つようになった。こんなエピソードを美談仕立てで伝える記事を何本か目にしたんだけど、上述した通り、16歳の時に歌手デビューは果たしているし、1960年代に入ってもソロ・アーティストとしての活動は継続していて、1962年には「It Might as well Rain until September」という曲をヒットさせている(全米22位、全英3位)。
自分のパフォーマンスに自信がなかった割に、一貫してソロ・アーティストとしての成功を目指して活動してきたようにも思える。この辺にずっと「違和感」があった。
しかし、今回、久しぶりに『つづれおり』を通して聴いてみて、キャロル・キングが歌に自信がなかったってのは、本当かもなぁと思った。
実際、1960年代後半、彼女がシンガーとして活動することに前向きだったかというと、決してそんなことはなかったようだ。
1968年に夫、ジェリー・ゴフィンと別れた後、一歩を踏み出したのは、ソロ・アーティストとしてではなく、バンド、ザ・シティのメンバーの一人としてだったし、1970年に発表したファースト・ソロ・アルバムのタイトルは『ライター Writer』だ。
この頃のキャロル・キングからは、「自分の本分はシンガーではなく、ソングライターなのだ」という強い自負が浮かび上がってくる。歌うのは、確かに二の次だったかもしれない。
では、なぜ、彼女がその後も歌い続けたのかと言うと、1960年代中盤以降、アーティストが自分たちで曲をつくることが普通となり、かつてのように職業作曲家として活動することが難しくなったことが原因だろう。
このままでは、自分のつくった曲を世の中に出す術がなくなってしまう。自分の曲を聴いてもらうには、たとえ本意ではなくても自分で歌うしかない。
キャロル・キングに一貫していたのは、「自分の曲を聴いてほしい」という一念だったんじゃないか。
1960年代のソロ活動も、「ソロ・アーティストとしての成功を目指して」いたわけではなく、純粋に自分のつくった曲を世に出したいがための行動だったのかもしれない。1970年代になっても、それは変わらなかった。ただ、そのためには、シンガーとしてのアイデンティティを新たに築く必要があった。でも、歌うの怖い。自信ない。
実は、『つづれおり』が、ニール・ヤング『アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ』、ジョニ・ミッチェルの『ブルー』と並び立つ傑作たりえたのは、キャロル・キングのシンガーとしての「自信のなさ」が鍵なんじゃないかと思う。
この時代のSSWには、シンプルなサウンドプロダクション、内省的な歌詞、ロック・スターの対極にある飾らないイメージといった共通点があるけど、加えて『つづれおり』『アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ』『ブルー』の3枚からは独特の緊張感が伝わってくる。
ニール・ヤングやジョニ・ミッチェルは、元々そういう資質をもったアーティストだと思うんだけど、キャロル・キングの場合は、『つづれおり』以外のアルバムから、このヒリヒリした空気を感じることはない。
ザ・シティ唯一のアルバム『夢語り Now That Everything’s Been Said』、ファースト・ソロ・アルバム『ライター』をこの機会に初めて聴いてみた。キャロル・キングのヴォーカルは、決して下手ではないんだけど、押しが弱いというか、無難な印象を受ける。
2枚ともすごくいいアルバムだし、聴く価値は十分あるんだけどね。
逆に『つづれおり』の次作『ミュージック Music』(1971年)、4枚目の『喜びは悲しみの後に Rymes & Reasons』(1972年)あたりになると、ヴォーカルに安定感があるし、説得力が加わったように思うのだけど、『つづれおり』にあったスリリングな感じに欠ける。
2枚とも佳曲揃いだし、チャートでも『ミュージック』が1位、『喜びは悲しみの後に』は2位と大ヒットしたんだけどね。
つまり、『つづれおり』の収録曲に通底する緊張感は、「ライター」から「シンガー・ソングライター」つまりパフォーマーへと脱皮しようという、キャロル・キングの覚悟と葛藤によるものなんじゃないだろうか。
「去りゆく恋人 So Far Away」「イッツ・トゥー・レイト It’s Too Late」「君の友だち You’ve Got a Friend」あたりの曲はスタンダードとして定着している名曲だけど、「パフォーマー、キャロル・キング」の挑戦という視点で考えると、聴くべきは「空が落ちてくる I Feel Earth Move」「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー」「ナチュラル・ウーマン (You Make Me Feel Like) A Natural Woman」の3曲だろう。
「空が落ちてくる」は、ファンキーで力強い、アルバムのオープニング曲。60年代に黒人アーティストに提供した曲のカヴァーかと思ってたけど、実際には『つづれおり』で初めて録音された曲だった。キャロル・キングのヴォーカルは黒人ほどのハリやケレン味はないけど、アーシーでエモーショナル。
「ウィル・ユー・ラヴ・ミー・トゥモロー」は、前述の通りシュレルズに提供した曲。「ナチュラル・ウーマン」は、1967年にアレサ・フランクリンが歌って、全米8位を記録している。いずれも、元のヴァージョンは大ヒットしていて、人々の記憶にしっかりと刻まれていたはず。そんな2曲、しかも、黒人シンガーが歌った曲にあえて挑戦したあたりに、キャロル・キングの「自分はパフォーマーなんだ」という決意を感じさせる。
この2曲においても、キャロル・キングならではの、あたたかさ、柔らかさが表現され、彼女がシンガーとしても独自の世界を築き上げたことが証明される。
うまく歌うのではなく、自分らしく歌うこと。それが葛藤の末に『つづれおり』で彼女が出した答えだった。そのアティチュードはSSWの時代にフィットし、喝采をもって迎えられることになる。そして、結果的に『つづれおり』は、この時代を代表する一枚となり、おっちゃんは数え切れないほど、繰り返し聴くことになる。
50年を経ても、その歌声は色褪せない。聴くべし(今回2回目)。
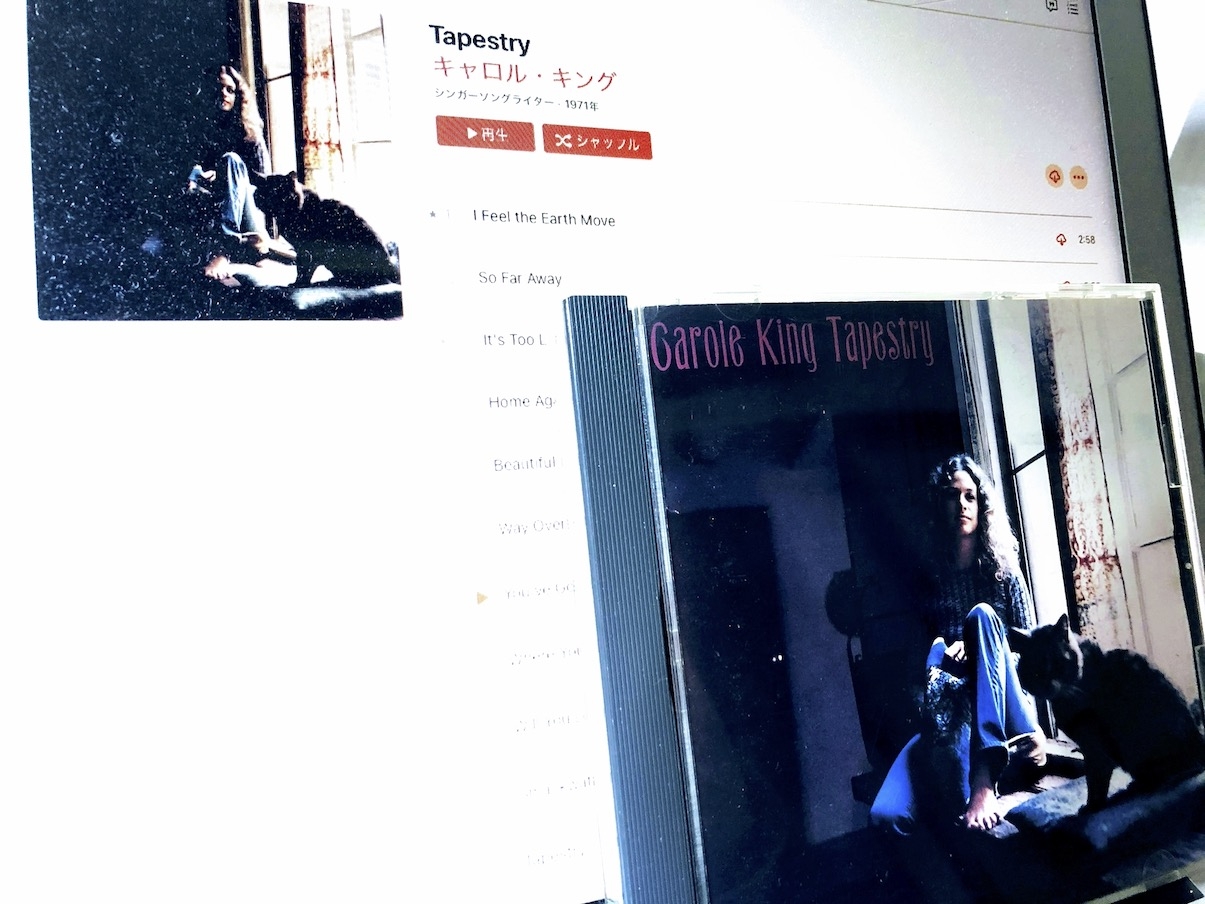
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★★


