音楽MUSIC
転がる石のように名盤100枚斬り 第66回#35 The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) - DAVID BOWIE 『ジギー・スターダスト』 - デヴィッド・ボウイ
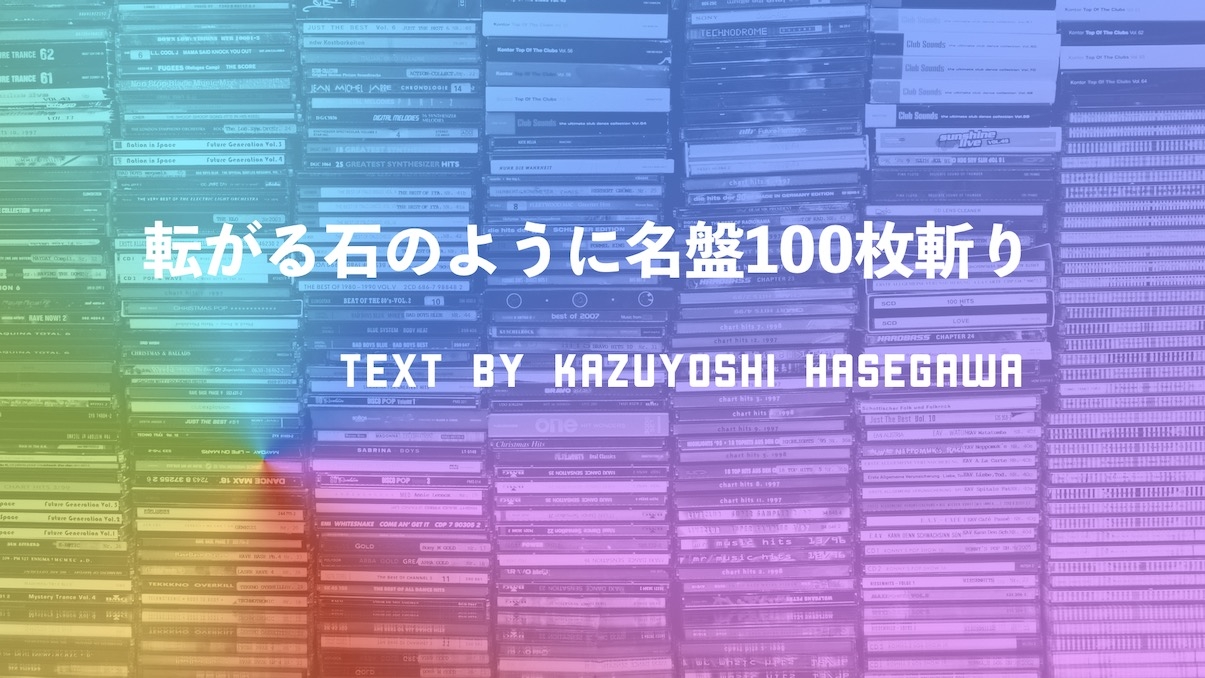
デヴィッド・ボウイがこの世を去って、5年が過ぎてしまった。
2016年1月10日、世界を駆け巡った訃報には、僕もガッツリ衝撃を受けた。その2日前、ボウイ69歳の誕生日にリリースされたアルバム『ブラック・スター Black Star』が、あまりに素晴らしい仕上がりだっただけに、そんなニュースは信じたくはなかったけど、『ブラック・スター』は間違いなく、ボウイが自身の「死」を意識したアルバムだったし、聴く者も、無意識のうちだったにせよ、それを感じ取っていたことも事実だった。
この年の冬は、ボウイ追悼の想いもあって、頻繁に『ブラック・スター』を聴いたけど、その後は、ほとんどかけていない。「死」の影が濃すぎて、普段何気なく聴くには重過ぎる。
ボウイ、ごめんね。
僕がボウイをリアルタイムで聴き始めたのは、五十路おじさんの例に漏れず『レッツ・ダンス Let’s Dance』(1983年)からだけど、それ以前からボウイのことは知っていて、それは、彼が宝酒造のテレビCMに出演していたからだった。
『レッツ・ダンス』リリースの同年に出演映画『戦場のメリークリスマス』(監督・大島渚)が公開されると、さらにメディアの注目が集まった。このころの日本のお茶の間において、デヴィッド・ボウイは、すごく身近で好感度の高いアーティストだったのだ。
今考えるとすごいことだな。
ボウイが日本という国と縁を深めるきっかけになったとも言えるアルバムが、今回のお題、『ローリングストーン誌が選ぶ史上最も偉大なアルバム』2003発表・2012改訂版35位の『ジギー・スターダスト』だ。
厳密に言うと、このアルバムに伴って行われたツアーの過程でボウイは日本に急接近する。
ニューヨーク公演の際にファッション・デザイナー・山本寛斎と出会ったボウイは、彼にステージ衣装を発注。1973年の日本ツアーから着用している。
これが今見ても奇天烈なデザイン。どうも、ボウイの方から、歌舞伎に代表される日本の伝統文化の要素を組み入れたいというリクエストがあったみたい。実際ステージでは、歌舞伎の早替わりの演出を採用している。
ボウイは寛斎のデザインが気に入ったようで、『ジギー・スターダスト』に続いてリリースされたアルバム『アラジン・セイン Aladdin Sane』(1973年)のツアーでも採用している(まぁ、この2作は兄弟みたいなもんだから、当然の成り行きだったかもしれないけど)。
斬新なルックスや発想は諸刃の剣で、この時期、アメリカでボウイが受け入れられなかったのは、メイキャップや寛斎の衣装で形作られたステージでの異形ぶりに、アメリカ人が引いてしまったからなんじゃないかと思っている。当時のアメリカは、ヨーロッパや日本以上に保守的だったんだな。
ちなみに、当時のスタイリングは、寛斎繋がりで高橋靖子が担当している。また、後に『ヒーローズ Heroes』(1977年)のジャケット写真を手がけることになる鋤田正義(福岡県・直方市出身)が初めてボウイを撮影したのは、1972年。『ジギー・スターダスト』リリースの直後だ。
ボウイの周り、日本人だらけ。
しかし、すべてはアルバム『ジギー・スターダスト』リリース後の話。アルバムには、日本のカルチャーの奇抜な応用はナッシングで、むしろ音楽的にはオーソドックスと言ってもいい。
僕がこのアルバムを初めて聴いたのは大学生の時だったんだけど、ジギー・スターダストという宇宙から来たロック・スターの物語云々よりも、ボウイのエモーショナルなヴォーカルと、キレキレのサウンドにしびれたのだった。
黙示録の風景を描き出す「5年間 5 Years」、”俺はワニやでぇ~”というイントロのフレーズからグッとくる「月世界の白昼夢 Moonage Daydream」、スタンダードとして燦然と輝く「スターマン Starman」、儚くも美しいバラード「レディ・スターダスト Lady Stardust」、そして、エモが極まる「ロックンロールの自殺者 Rock’N’Roll Suicide」などなど、全曲素晴らしい。
各ナンバーの邦題も味わい深い。なにせ、最初にレコードがリリースされた際のアルバムの邦題は「屈折する星屑の上昇と下降、そして火星から来た蜘蛛の群」だものね。
若いころは、パンキッシュなサウンドが炸裂する「君の意思のままに Hang Onto Yourself」とファンキーなロックンロール「サフラジェット・シティ Suffragette City」をよく聴いていたが、「サフラジェット・シティ、婦人参政権の街・・・・・・なんだそれ?」てなもんで、正直言って歌詞の内容はあまり気にしていなかった。
そこで、今回、久しぶりに聴くに当たって、まずはジギーの物語を理解することにしましたよ。こういう時に役立つのがCDのライナーノーツ。
「宇宙から来た異星人が造物主の手によってロックスターに仕立て上げられ、そのエゴが頂点に達したときから破滅の道を辿り、自らの手で自分を抹殺する」(信貴朋子・東芝EMI『ジギー・スターダスト』ライナーノーツより)
うむ。なんとなくそんな話なんじゃないかと思っていたよ。しかし、トンデモな世界ですね。
歌詞もちゃんと読んでみた。「ジギー=ボウイ」としてよく語られるけど、歌詞を追ってみるとアルバムにおけるボウイの立ち位置はあくまでも客観的なストーリー・テラーだった。曲によって、ジギーも含めたいくつかのキャラクターの視点を借りながら、物語をつむぎ出していく。
たとえば、オープナーの「5年後」。「世界の終わり」を突きつけられた「名もなき人々 the nobody people」が悲嘆に暮れる様子を客観的に描いているが、この曲の語り手は、このアルバムの創造主であるボウイ自身だ。
「月世界の白昼夢」「スター」「サフラジェット・シティ」はおそらくジギー目線。「スターマン」や「レディ・スターダスト」はジギーのファンの体験か。タイトル・トラック「ジギー・スターダスト Ziggy Stardust」はジギーのバンド・メンバーのつぶやき。
楽曲を聴きながら、全体を通して歌詞に目を通すと、いくつか「?」が浮かんでくる。
「5年後」では、”地球には5年しか残されていない、世も末やん、みんな死んじゃうんよー”と歌われているけど、その後、地球はどうなっちゃったんだろう。アルバムを最後まで聴いてもまったくわからない・・・・・というか、「世界の終わり」には、まったく触れられていない。終末論自体が、誰か(ジギー?)の妄想だったんだろうか?
ほかにもモヤモヤするところがあったので、WEBにアップされている好事家の方々のブログにも目を通してみた。
これまで、「レディ・スターダスト」については、ジギーのデュエット相手の女かいなとか、まったく歌詞を無視したまま、適当に考えていたんだけど、この表現は、ジギーが女性のようにメイキャップをしてステージに上がることを示しているんだな。これはちゃんと歌詞を読めばわかることだった。
問題は、「サフラジェット・シティ」だ。こっちは歌詞を何回読んでも意味がわからん。
“お前さぁ、俺にもたれかかるなって/チケット買う金もないくせに/俺は婦人参政権の街に戻るとこなんだからさ”
わからん。
WEBにアップされているいくつかのブログを読むと「Suffragette City」ってのは、売春宿のメタファーなんだそうだ。
なるほど。知らんかった。
最後のシャウト”Wham Bam, Thank you Mom!”の「Wham Bam」はそのまま訳すと「どったんばったん」みたいなニュアンスになるんだけど、ここでは「慌ただしいセックス」を表しているらしい。
なるほど。勉強になる。好事家のみなさん、すごい。
アルバム全体のストーリーの解釈も人によってさまざまで、上記に紹介したCDのライナーノーツのように「自ら命をたった」という説もあれば、暴徒と化したファンに殺されたという筋書きもいくつか目にした。
ポイントは、ラストの「ロックンロールの自殺者」だろう。ほかの曲については、WEBのおかげであらかたモヤモヤは解消されたんだけど、この曲が意味していることがピンと来ず、最後まで首をひねっていた。
曲の序盤では、落ちぶれてしまったジギー・スターダストの描写が積み重なる。”Your’e a rock’n’roll suicide お前はロックンロールの自殺者なんだよ”というフレーズは、ロックの夢に殉じたジギーへ手向けられたのだろう。
つまり、ジギー・スターダストは、死んでないんじゃないの?
よくわかんないのが、最後に繰り返されるボウイの絶叫だ。
歌詞を無視して聴いてた時は、ステージの上からジギーがオーディエンスに手を伸ばして”君たちは孤独じゃない/僕の手をつかむんだ”と歌いかける感動的なシーンが頭に浮かんでいたんだけど、どうもそうじゃないみたい。
“僕と行けるところまで行こう/そうすればお前は一人ぼっちじゃない/(素晴らしい)/君は素晴らしい/手を伸ばすんだ”
曲の流れから判断すると、「お前」はロック・スターとしての輝きを失った、「ロックンロールの自殺者」ジギーだよね。だったら、「僕と一緒だったらひとりぼっちじゃない」と声を枯らす「僕」はいったい誰なんだろう?
バンド・メンバーはジギーを見捨ててしまった。ファンは、彼を殺さなかったにしても、ジギーを偽物の救世主だと断罪している。とすると、答えは一つ。ジギーを救済しようとする「僕」は、創造主であるデヴィッド・ボウイ以外にいない。
「お前は一人ぼっちじゃない」と歌った時点で、ストーリー・テラーとしてのボウイは消滅し、ジギー・スターダストの世界に取り込まれる。そして、ボウイが伸ばした手をジギー・スターダストが握った時に、初めて二人は一体化する。そして、新たな旅が始まる。
実際、アルバム・リリース後のツアーで、ボウイは完全にジギー・スターダスト化してしまう。日本公演の際に対面した坂東玉三郎は、ボウイがステージを降りてからも別人格であるジギーを演じ続けるていることに異様な印象を受けたようだ。
ボウイのジギー・スターダスト化に大きな力を与えたのが、山本寛斎をはじめとする日本のクリエイターだったことは前に述べた。
結果的に、『ジギー・スターダスト』は一人のアーティストが、自分の想像したキャラクターに同化していく過程を描いたアルバムになってしまった。
そこには、デヴィッド・ボウイという人の「業」みたいなものを強く感じる。この時から、演じること、変わり続けることが、アーティストとしてのボウイのアイデンティとなる。もがき苦しみながらも、アップデイトし続けることを自らに課したのだ。
その旅は、この後、2016年まで続く。『ジギー・スターダスト』は、そのスタートにふさわしいロック史に残る一枚だ。ということで・・・・・・

おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★★


