音楽MUSIC
長谷川和芳 | 転がる石のように名盤100枚斬り 第69回#32 Let It Bleed (1969) - THE ROLLING STONES 『レット・イット・ブリード』 - ザ・ローリング・ストーンズ
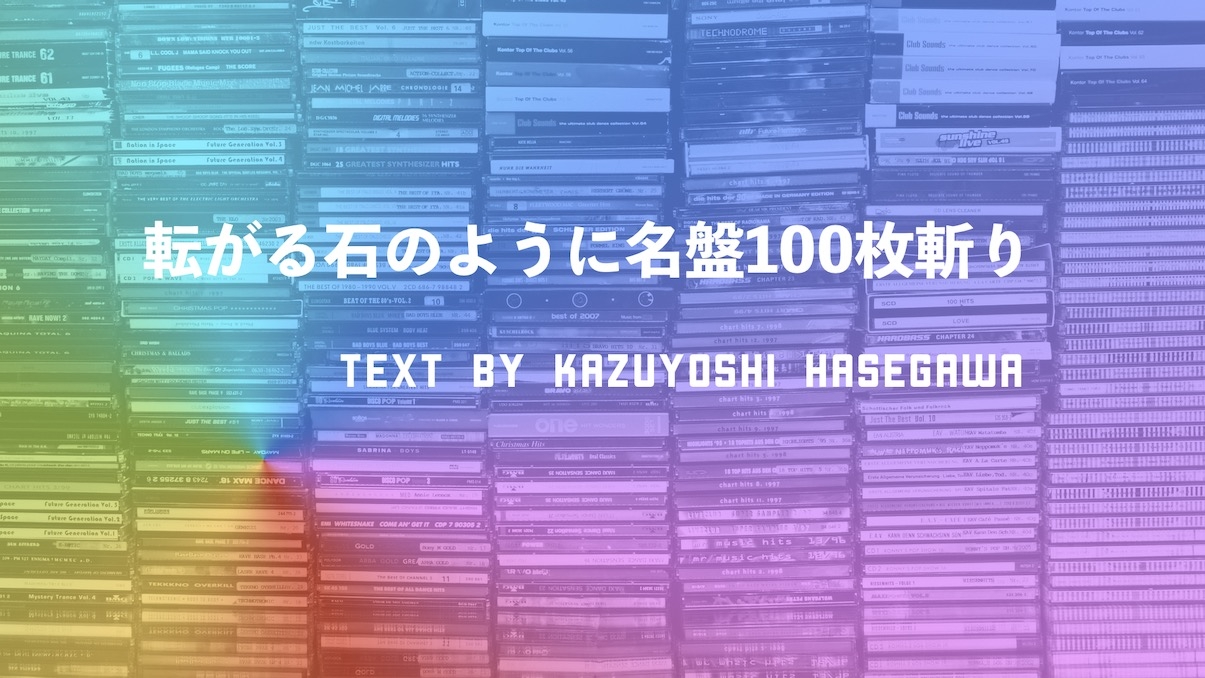
小学6年生の時の僕の愛読書が、『青春音楽グラフィティ』(集英社文庫)だったことは、この連載の第1回でも書いた。この文庫本は洋楽アーティストのバイオグラフィを紹介したもので、当然ザ・ローリング・ストーンズのページもあった。なぜか「オルタモントの悲劇」にかんする記述にスペースを割いていたことを記憶している。
「オルタモントの悲劇」は、1969年に開催したストーンズ主催のフリー・コンサートで、会場の警備を担当していたヘルズ・エンジェルスがオーディエンスを刺殺したという事件。当時、『ローリング・ストーン』誌は「ロックン・ロールにとって最悪の日」と報じ、現在では、60年代のラヴ&ピース幻想の終焉を告げたとされている。
『青春音楽グラフィティ』でこの事件を読んだ当時は知らなかったんだけど、このコンサートがオルタモント・スピードウェイで開催された1969年12月6日は、僕が生まれた日だったりする。「オルタモントの悲劇」の落とし子!
なんと、このフリー・コンサートの開催中に4件の出産が記録されているらしい。同年同月同日生まれのみんな、元気かなぁ。
小学6年生の僕にとって、「オルタモントの悲劇」の印象は強烈で、「ストーンズってのはおとろしいバンドやね」と思ってしまった。「ヘルズ・エンジェルス」がなんなのかもわかってなかったけどね。「オーディエンスが殺されているのを横目に見て、ステージ上で平然と演奏を続けるストーンズの面々」という画が浮かんだ。冷酷なり、ザ・ローリング・ストーンズ。
実際にストーンズが事件を知ったのは、ステージを降りた後だった。そりゃ、そうだ。
しかし、そんなこんなで、禍々しい印象が頭にこびりついちゃって、その後もなんとなくストーンズは敬遠。ちょっとは聴くようになったのは、高校生になってからだった。
『ローリングストーン誌が選ぶ史上最も偉大なアルバム』2003発表・2012改訂版32位『レット・イット・ブリード』は、「オルタモントの悲劇」と関連づけて語られるアルバムだ。上記のような経緯もあって、僕はこれまでこのアルバムを通して聴いたことことはない。
「オルタモントの悲劇」の舞台となったフリー・コンサートは、『レット・イット・ブリード』発売に伴って行われたアメリカ・ツアーの一環だった。アルバムがイギリスで発売されたのは、「オルタモントの悲劇」の前日(アメリカはその1週間前)。「オルタモントの悲劇」の呪いがかかったアルバムなんだろか。
『ローリング・ストーン』誌のレヴューやWikipediaによると、このアルバムで歌われているのは「戦争」「レイプ」「殺人」「麻薬中毒」などなど。物騒なワードが並ぶ。
「アルバム全体を通して黙示録的な世界観が燃え盛っている」(『ローリング・ストーン』誌レヴュー)
ミック・ジャガーは、毎日テレビ画面から大量に流されるベトナム戦争の映像に感化されたことを告白している。
ミック曰く「暴力的な時代だったんだよ」
「オルタモントの悲劇」が起こったのも時代の必然だったということか。
きっと、このアルバムでは、「悪魔を憐れむ歌」+「ストリート・ファイティング・マン」(いずれも前作『ベガーズ・バンケット』に収録)+ドアーズの「ジ・エンド」みたいな世界が展開されるに違いない。暴力と絶望が支配する世界。
覚悟を決めて聴いてみた。
結論から言う。ストーンズ・ファンのみなさんからのお叱りや「わかってねぇなぁ」という冷たい視線を恐れずに言う。
『レット・イット・ブリード』は、すごくおしゃれなアルバムです。言葉を変えると、洗練されている。禍々しさはゼロ。むしろ聴き終わると清々しささえ感じる。
確かに、『ローリング・ストーン』誌のレヴューにもある通り、いくつかの曲では殺伐とした世界が歌われている。「戦争」「レイプ」という言葉が出てくるのは、オープニングを飾る「ギミー・シェルター Gimme Shelter」だ。
「オルタモントの悲劇」の瞬間も収めたドキュメンタリー映画のタイトルは、この曲から取られている。
“戦争なんてのはさぁ、坊や達
銃を一発撃てば、すぐに始まってしまうんだぜ
銃の一発で十分だ
見ろよ、まさに今、炎が俺たちが住む街角を覆っていく
赤い炭のカーペットみたいに通りが焼けていく
狂った雄牛は行き場所を失う”
歌詞に目を通すと、ベトナムの戦場を想起させる描写が続いている。
しかし実際に曲を聴くと、殺伐な感じばかりでもない。
イントロの透明感のあるギターに、ギロの音と幽玄な感じのコーラスがかぶってくる。徐々にテンションが上がっていき、ミック・ジャガーとメリー・クレイトンのヴォーカルが炸裂。軽快なパーカッションにピアノが曲に厚みを与える。ついには、すべての音が一体となってドライヴしていく。
要は、「1969年の時代背景」なんて抜きにして、純粋に音楽としてカッコいい。聞いてると高揚感が込み上げてくる。
『ローリング・ストーン』誌のレヴューに挙がっているキーワードのうち、「殺人」は、1962~64年に世間を騒がせた「ボストンの絞殺魔」、アルバート・デサルヴォを歌った「ミッドナイト・ランブラー Midnight Rambler」を指すんだろう。「麻薬中毒」は、クスリがもたらす高揚感とその反動である禁断症状を表現した「モンキー・マン Monkey Man」だ。
しかし、「ギミー・シェルター」同様、シリアスな題材だからって、聴いていて気が滅入ることはない。「ミッドナイト・ランブラー」は、ハーモニカの音がユーモラスな印象を与えるブルース・ナンバーだし、「モンキー・マン」は、キレのあるミックのヴォーカルも聴きどころの浮遊感のあるロックン・ロールだ。
聴く前にもっていた「暴力的」「禍々しい」なんて先入観は、一度アルバムを通して聴くと、きれいさっぱり洗い流されてしまった。
ラストに収められている「無情の世界 You Can't Always Get What You Want」もタイトルは殺伐系だけど、聴いてみると、グルーヴィでポジティヴな曲なのだった。一種のカタルシスさえ感じる。アルバムの最後を飾る、大団円という言葉がふさわしい名曲。
この曲は、昨年4月にレディ・ガガの呼びかけで行われたヴァーチャル・コンサート『One World: Together at Home』において、リモート環境で演奏された。
ミックを皮切りにメンバーが順番に画面に入ってくるという趣向だったけど、最後にチャーリー・ワッツがカットインすると、彼だけはエア・ドラム状態で、世界中の音楽ファンがずっこけたのも記憶に新しい。
『One World~』でこの曲が演奏されたのは、世界が決して「無情」ではないと伝えたかったからだろう。
タイトルにだまされて、若者のフラストレーションがテーマのように思いがちだけど、
”欲しいものがいつも手に入るとは限らない
でも、時にはトライしてみたら、欲しいものが手に入ってたりするかもよ”
なんて一節もあって、しんどいことには変わりないけど、最後に一縷の希望を掌に載せてくれるような内容なのだった。
「やさしい世界」やん。
これらの曲も含め、このアルバムに収録されている曲は、かなり緻密にサウンドが組み立てられている。厚みというか深みがある。加えて、アルバム全体の構成も見事。特にLPレコードのB面である「ミッドナイト・ランブラー」~「無情の世界」の流れはすごくスムース。このへんが「洗練された」印象に繋がっている。
前作に続いてプロデュースを担当したジミー・ミラーの貢献度はかなり大きいんじゃなかろうか。
『レット・イット・ブリード』がリリースされた1969年といえば、9月にザ・ビートルズが『アビー・ロード』を発表。レコードB面に収録されているメドレーは彼らの最高傑作の一つとされる。
『レット・イット・ブリード』のB面は、『アビー・ロード』ほどこれ見よがしではないけれど、よほど粋だし大人の余裕を感じる。
「黙示録的な世界観」なんていうレヴューや、「ベトナム戦争がー」というミックのつぶやきや、「オルタモントの悲劇」にまつわるあれこれは、一旦脇に置いて、純粋に音に耳を澄ませた方が、このアルバムの真価が伝わるんじゃないだろうか。
予想以上に文句なしの名盤でした。
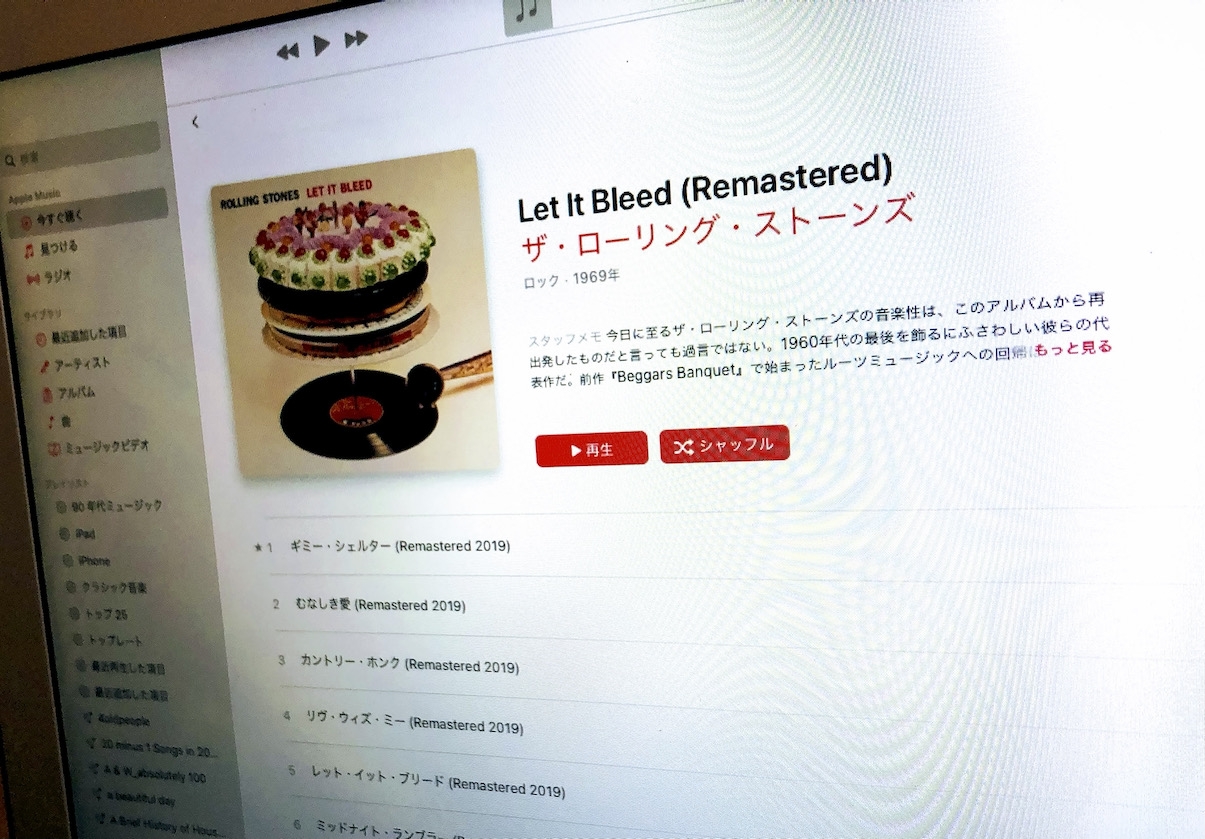
おっちゃん的名盤度(5つ星が満点):★★★★★


